本記事では、福利厚生サービスについてQ&A方式で解説しております。
福利厚生サービスの導入目的についてよくある疑問


A.福利厚生サービスとは、企業側が従業員に対して給与以外の報酬やサービスを提供する仕組みのことを指します。
福利厚生サービスでは、様々な福利厚生の導入や管理をサポートすることができます。
福利厚生制度は、従業員だけでなく、その家族まで利用できるものもあるため、導入することでエンゲージメントの向上などの様々なメリットがあります。
近年はテレワークを取り入れている企業向けの福利厚生も登場しています。

Q.福利厚生サービスの導入目的とは?

A.
【企業定着率を向上させる】
様々な福利厚生が取り入れられることで、従業員は働きやすさが向上します。
また、従業員だけでなく、その家族も利用できる福利厚生を取り入れれば、企業側が従業員のことを大切に扱ってくれていると実感することができ、エンゲージメントが高まります。
企業への貢献意識が高まることで、1つの会社で長く働きたいと従業員は感じるようになり、企業定着率が向上します。
【法人税の節約】
福利厚生は、要件を満たすことで非課税対象となります。
福利厚生費を経費として計上することができれば、法人税の計算から除外することが可能となるため、法人税の節約につながります。

Q.福利厚生サービス導入で得られる効果とは?

A.
【求人応募率の向上】
働き方や価値観の多様化に伴い、就職活動において福利厚生の内容を重視する人が増えています。
福利厚生サービスを導入することで、他社との差別化を図り、採用活動におけるアピールポイントとすることができます。
ユニークな福利厚生を取り入れていたり、自社の事業とマッチした福利厚生を取り入れたりすることで、自社と親和性の高い人材が応募してきてくれる可能性も高まります。
【企業のイメージアップ】
福利厚生が充実していることで、従業員のことを大切にしていると感じてもらえるため、イメージアップにつながるでしょう。
社食サービスやオンラインフィットネスなどを取り入れることで、健康経営にもつながり、健康経営銘柄に認定されれば投資家や取引先からの印象も良くなり、新規取引の獲得につながるかもしれません。
【従業員の健康管理が可能になる】
近年、テレワークなどの在宅勤務を導入する企業が増えたこともあり、運動不足や栄養バランスの偏りが問題となっています。
福利厚生として栄養バランスの取れた食事を取れる社食サービスや、オンラインフィットネスなどのサービスを取り入れることで、従業員の健康管理につながります。

Q.目的に合った福利厚生サービスの選び方とは?

A.
【目的を明確にする】
福利厚生サービスを導入する際は、まず目的を明確にしましょう。
ただ導入するだけでは、福利厚生の利用率を高めることができません。
従業員の健康管理を実現したいのであれば、社食サービスやジム施設などのサービスを取り入れると良いでしょう。
社内でアンケートを実施し、どのようなサービスが求められているのかを調査することをおすすめします。
【会員数や提携しているサービスの確認】
福利厚生サービスは、基本的に登録している会員数が多いほど提携している施設も多い傾向にあります。
そのため、サービスの比較検討を行う際は、どれくらいの会員数があるのかを確認しましょう。
どのようなサービスを利用できるか、割引率は高いのか、といった点も併せて確認することをおすすめします。
【料金の確認】
福利厚生サービスは、大きく分けて2種類に分類されます。
パッケージプランは会員数に応じて料金が発生する形式のものが多いため、利用人数が増えるほどにコストが高額になる傾向があります。
カフェテリアプランは利用するサービスごとに料金が発生するものが多いため、導入したいサービスを想定した上で見積もり依頼すると良いでしょう。
【サポート体制の確認】
福利厚生サービスはただ導入したからといって利用率が高まるわけではありません。
導入後に、社員への周知活動をサポートしてくれるようなサービスを選ぶことで利用率を高めることできるでしょう。
また、社員からの問い合わせに対応してくれるサービスや、多言語に対応しているサービスなどもあるため、導入前にどのようなサポート体制があるのかを確認しておくことが重要です。
福利厚生サービスの費用についてよくある疑問

Q.福利厚生サービスとは?

A.福利厚生サービスとは、従業員への福利厚生をアウトソーシングすることができるサービスです。
オンラインフィットネスや介護、育児サポートから社内カフェ、レジャー施設の利用まで、福利厚生として利用できるサービスは幅広く、利用する福利厚生サービスによって異なります。
福利厚生サービスは、従業員だけでなく、従業員の家族まで利用できる場合もあるため、従業員のエンゲージメント向上に貢献します。
自社で様々な福利厚生を取り入れようとすると、サービスごとに管理をする手間が発生しますが、この手間をアウトソーシングすることができるため、総務部の業務負荷を軽減できる点も特徴的です。

Q.福利厚生サービスの種類は?

A.福利厚生サービスは、大きく分けて2種類に分類されます。それぞれの特徴を解説します。
【パッケージプラン】
パッケージプランは、カテゴリーごとに様々な福利厚生をパッケージ化して提供するプランのことを指します。
パッケージプランは、自社で福利厚生を探す手間がなく、導入における手続きのほとんどが福利厚生サービスに任せることができる点がメリットです。
しかし、予め決められたパッケージを利用することとなるため、自社で独自に福利厚生を取り入れていきたい場合には向きません。
【カフェテリアプラン】
カフェテリアプランは、企業が導入したい福利厚生を柔軟に導入することができます。
福利厚生サービスを導入する際に、どのような福利厚生を取り入れたいかを相談し、手配や運用を代行してもらうプランです。
パッケージプランと比べ、自社で福利厚生を選定する手間は発生しますが、企業ごとにメニューをカスタマイズすることができるため、従業員からのニーズが高い福利厚生を、その時々のトレンドに沿って導入することができます。

Q.福利厚生サービスの費用は?

A.福利厚生サービスの導入にかかる費用をプランごとに比較すると以下の通りです。
・パッケージプラン:月額300円〜1,000円/人
・カフェテリアプラン:月額100円〜400円/人
上記はあくまでも目安ですが、福利厚生サービスを導入する際は、パッケージプランの方が費用が高額になる傾向があります。
発生する費用としては、「入会金」「システム設定費用」「プラン利用料」「ポイント原資」などが挙げられます。
サービス利用料は従業員ごとに月額が発生するものと、1社につき料金が発生するものがあり、大企業向けの福利厚生サービスでは、従業員単位で料金がかかるサービスが多くなっています。
入会金の相場としては、2万円〜100万円程度となっており、システム設定費用の相場は10万円〜100万円となっていますが、いずれも従業員規模によって異なるため、参考としてください。

Q.失敗しない福利厚生サービスの選び方とは?

A.福利厚生サービスの導入にあたっては以下の点に注意すると良いでしょう。
【目的を明確にする】
福利厚生サービスを導入する際は、目的を明確にすることが重要です。
従業員の育児・出産に伴う途中離脱を福利厚生でサポートしたいのか、メンタルヘルスを解消したいのかなど、目的によって最適な福利厚生は異なるため、まずは自社の事業の特徴や、社内環境の確認などから始めると良いでしょう。
【会員数や提携しているサービスを確認】
会員数が多い福利厚生サービスほど、提携している施設数も多いため、幅広い福利厚生を取り入れることができます。
どのような企業と提携していて、どれくらいの割引率で利用できるのかなども確認しておくと良いでしょう。
外国人のメンバーが多い企業の場合、多言語対応しているかも確認しておくことをおすすめします。
【料金体系のチェック】
福利厚生サービスは、パッケージプラン・カフェテリアプランそれぞれで料金が異なるため、導入においては予算を明確にした上で、見積もりを依頼することが重要です。
また、サービスによって支払い方法も異なります。
月額で支払うものや、年間契約で一括払いとなっているものなど様々にありますので、自社の負担が少ないものを選ぶと良いでしょう。
【サポート面の確認】
実際に福利厚生サービスを導入してみて、自社独自の福利厚生を取り入れたいのでプランを変更したいというニーズは将来的に発生する要素です。
そのため、プランの見直しやカスタマイズに柔軟に対応できるサービスを選ぶと良いでしょう。
また、サービスによってサポート体制には差があり、電話サポートのみの場合やメール・チャットでのサポートも実施しているサービスもありますので、比較検討のポイントにすることをおすすめします。





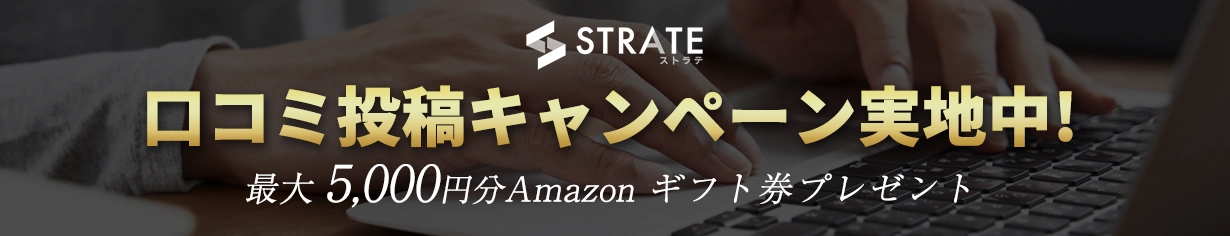
Q.福利厚生サービスとは?