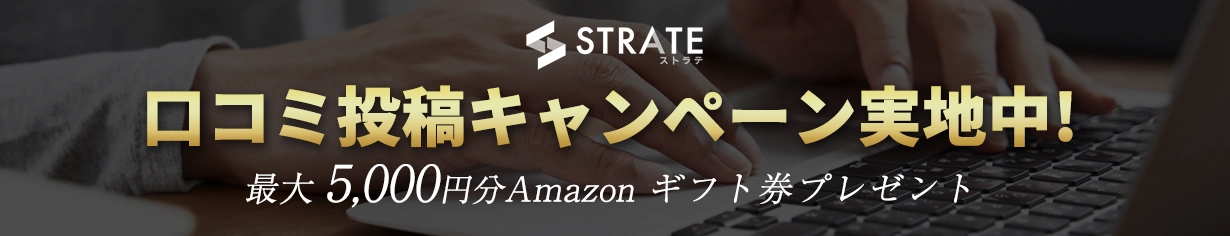スマートフォンの急激な普及もあり、オンライン上での決済を行う方も増えたのではないでしょうか。
オンラインでの決済などにおいては不正対策やセキュリティ強化、業務効率化の観点から「eKYC」を活用するケースが増えています。
近年聞かれるようになったeKYCという言葉、聞く機会はあっても意味はわからないという方も多いと思います。
本記事ではeKYCについて、基本的な意味や導入するメリット、おすすめのeKYCサービスなどを紹介しますので参考にしてください。
eKYCとは?
eKYCとはelectronic KYC(Know Your Customer)の略で、日本語での読み方はそのまま「イー・ケー・ワイ・シー」となります。
従来からあるKYCという本人確認手続きをオンライン上で実現するための仕組みで、2018年に金融のデジタル化戦略として改正された「犯罪による収益の移転防止に関する法律」において本人確認がオンラインでも認められることが決まったことを受けeKYCが普及するようになりました。
eKYCを導入している業界としては銀行などの金融機関や会員向けサービスを提供している企業などが挙げられます。
そもそもKYCとは?
KYCとは、銀行などの金融機関において口座開設時に義務つけられる本人確認手続きのことを指します。
この本人確認は「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に準拠するものとなっています。
マネーロンダリングの防止やテロに対する資金供与などの不正を防止するためには、重要な取引時には相手型の身元確認を徹底し、確認•結果の記録を残しておく必要があります。それ故に銀行などでは一定の取引を行う場合には相手型の氏名や住居、生年月日など本人特定事項を確認する義務が発生します。
KYCのKnow Your Customerとは、本人確認によって顧客の身元を確認するという意味になるのです。
おすすめの類似eKYCツール
類似サービス: ネクスウェイ本人確認サービス
(4.5)
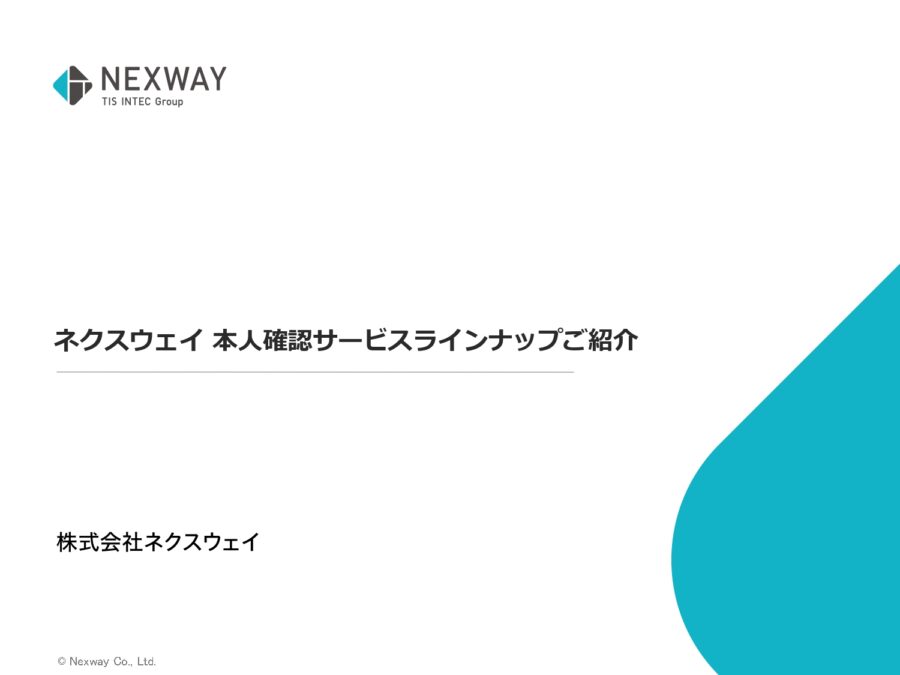
| 月額費用 | 要問い合わせ | 無料お試し | 要問い合わせ |
|---|---|---|---|
| 初期費用 | 要問い合わせ | 最低導入期間 | 3ヶ月〜 |
ネクスウェイ本人確認サービスは、オンラインで本人確認から書類の目視によるチェック、その他KYC業務に必要な工程をワンストップでサポートしてくれるため、本人確認作業に人員を割くことが難しい方という方にもおすすめです。
スムーズなオンライン確認を実現
ネクスウェイの本人確認サービスでは、スマートフォンで撮影した本人確認書類と顔写真だけでスピーディーな本人確認を実現します。
チェック業務をアウトソーシングできる
ネクスウェイ本人確認サービスでは、これらの業務をアウトソーシングすることができ、BPOセンターの専任スタッフが犯収法に準拠したフローで、eKYC後の本人確認業務を代行してくれます。
eKYCに対応できない顧客もフォロー
「本人確認・発送追跡サービス」を利用することで、セキュリティに配慮した迅速な本人確認書類の郵送を可能とし、顧客との取引開始までにかかる時間を短縮させることができます。
eKYCの導入メリット
サービスの利用や提供が早期化する
従来のKYCでは口座開設やクレジットカードの発行時に手間と時間がかかっていました。
オンラインで申請すること自体はできても、本人確認には身分証明書の写しを郵送で送ったり、必要な書類の受け取りをしなければいけないなどの手間がかかり、当然ながら時間もその分かかってしまいます。
申し込みから実際にサービスを受けられる様になるには数日かかってしまい、このタイムロスはサービス提供側にも利用者側にも大きなデメリットでした。
eKYCを導入すれば、その場で本人確認が可能となりサービスの提供も本人確認が終了次第すぐに行えるようになります。
このサービス提供•利用の早期化は非常に大きなメリットでしょう。
申し込みの完了率が上がる
従来の本人確認手続きには、身分証明書の写しなどを郵送する手間があり、申し込みを結局やめてしまうというケースは少なくありませんでした。
さらに、書類を提出したはいいけれど不備があり、再度必要書類の提出を求められたことで面倒くさくなってしまい申し込みをやめてしまったというユーザーも多いでしょう。
eKYCを導入すればオンラインで申し込みが完了できることで申し込みの完了率が向上するだけでなく離脱率低下も期待できます。
業務効率化やコスト削減を実現できる
eKYCを導入することで、本人確認書類の真偽の判断や顔写真の称号などを自動化することができるため、確認作業の効率化が期待できます。
もちろん最終的な確認は人が行うことになってもシステム上で簡単に確認できるようになるため、紙の書類を確認する場合よりも作業における負担は少ないでしょう。
また、従来であればサービス提供側、またはユーザーが負担していた本人確認書類の送付にかかる郵送費や封筒代金、保管にかかるコストも削減できる点もメリットと言えます。
不正認証のリスクがない
eKYCサービスでは、容貌から人物の特徴を照らし合わせ本人かどうかを確認するため、本人確認書類の写真とともに本人の容貌写真を要求されることがあります。
そういった点においても、eKYCは不正がされにくく、セキュリティ面を非常に信頼できるサービスです。
ロボットや人形ではなく、人間であるかどうかのチェックとして、まばたきをしているかどうかの確認などを行うツールも多く、生体的特徴をしっかりと照合するシステムが構築されているため、不正認証のリスクはほぼクリアできると言って間違いないでしょう。
eKYCの導入デメリット
ユーザー側の機器操作トラブルのリスク
デメリットの1つ目として、eKYCを行うユーザー側の機器操作トラブルリスクが挙げられます。
eKYCは時間と場所を選ばずに本人確認できる点が大きなメリットですが、ユーザー自身が自発的に操作をすることで成立するシステムです。
スマホやパソコンを持っていないユーザーはeKYCを利用することが不可能です。
ユーザーが使用するデバイスのOSバージョンが古い場合、事業者が提供するアプリやシステムに対応できないというリスクも考えられます。
また、eKYCはリアルタイムでの撮影が必須であるシステムなので、ユーザーの撮影環境や状況次第では、画像処理のトラブルにも注意を図る必要があります。
課金体系によってはコストが高くなる
eKYCサービスを導入することでコストが高くなることも考えられます。
eKYCには、ブラウザ版とアプリ版の2種類がありますが、ブラウザ版はデータを連携させる必要があります。
アプリ版はアプリを開発する費用がかかるため、これらeKYCを導入する際の開発費用が月額利用料とは別途で発生するということを十分に理解しておきましょう。
また、求める仕様やサービス内容により、開発費用・月額費用ともに従来の本人確認方法よりコストがかかる可能性も考えられなくありません。
eKYCサービスの選び方のポイント
| 製品名 | 参考価格 | 無料トライアル |
|---|---|---|
| ネクスウェイ本人確認サービス | 要問い合わせ | – 要問い合わせ |
| Digital KYC | 要問い合わせ | – 要問い合わせ |
| LINE eKYC | 要問い合わせ | – 要問い合わせ |
| TRUSTDOCK | 要問い合わせ | – 要問い合わせ |
| ProTech ID Cheker | 要問い合わせ | – 要問い合わせ |
本人確認方法が適切か
本人確認方法が適切かどうかは、eKYCを比較する際には非常に重要です。
例えば、
- 「本人確認書類の写真」と「本人の顔写真」
- 「本人確認書類のICチップ読み取り」と「本人の顔写真」
上記2つはどちらも適切な本人確認方法です。
eKYCサービスを比較するにあたって、どのような本人確認方法が行われているかを必ず確認しましょう。
対応している本人確認書類の把握
対応している本人確認書類も把握しておきましょう。
本人確認書類としては、以下が一般的です。
- 運転免許証
- マイナンバーカード
- 写真付き健康保険証
- パスポート
特に運転免許証とマイナンバーカードが主流ですが、ニーズによっては、写真付き健康保険証やパスポートにも対応している場合があるのでしっかり確認しておくと良いでしょう。
端末・OS・ブラウザに対応しているか把握
どの端末・OS・ブラウザに対応しているかも必ず把握しておくべきです。
パソコンかスマホどちらかの端末のみで本人確認を行う場合や、対応していないOSやブラウザがある場合もあるため、自社の顧客がどのような端末で本人確認するのか、OSやブラウザは何を使っているのかに着目し、対応しているサービスを選定しましょう。
コスト感は適切か
どれだけ充実したサービスでも、コストが見合っていなければ持続は難しいものです。
予算内でサービスを利用できるかどうか、また、コスト優先でサービスの内容が要件を満たしているかなど、eKYCの導入目的に合わせて、適切なサービスを選択するべきです。
簡単に操作可能か
操作を簡単に行えるかどうかもeKYCの導入にあたって、非常に重要です。
本人確認が簡単にできるか顧客からの目線で考え、高齢者が利用する場合も、操作がしやすいなど、サービスの特徴を捉えておきましょう。
eKYCのおすすめサービス
ネクスウェイ本人確認サービス
特徴
株式会社ネクスウェイが提供している本人確認サービスです。
特徴的なのは本人確認書類と顔写真での本人確認を行うeKYCだけでなく、付随する本人確認業務のアウトソーシングにも対応している点です。
eKYC~反社チェック~書類審査~転送不要郵便の発送、確認記録の保存までをワンストップで提供しています。
自社で法律要件の学習にさけるリソースがない場合やセキュリティに不安がある場合、確認作業などの事務作業をアウトソーシングしてコア業務に集中したい場合には特におすすめでしょう。
料金
- 初期費用:要問い合わせ
- 月額料金:要問い合わせ
※料金情報は2022年1月時点のもの

K.N様
業種:IT/会社規模:101人〜300人
導入している企業も大手が多く安心できます
今までは送付してもらった本人確認書類の確認から承認まで日数を要していたので、承認の連絡を入れる際にはユーザーが離脱してしまい別の類似サービスや競合サービスへの登録に流れているケースがありましたが、こちらのサービスを導入してからはユーザーへの最終承認連絡までの時間が大幅に減り、登録途中での離脱率の改善につながっています。
詳しくはこちら
Digital KYC
特徴
スマートフォンなどのカメラを用いてオンライン上で本人確認ができるサービスで、その認証精度の高さに定評があるサービスです。
導入先での累計利用回数1,000万回、2021年度MM総研大賞受賞という実績があり確かな導入効果が期待できます。
ライブネス判定によるなりすましなどの不正防止を実現し、本人確認書類は免許証だけでなくマイナンバーカードや在留カードにも対応しています。
料金
- 初期費用:要問い合わせ
- 月額料金:要問い合わせ
※料金情報は2022年1月時点のもの
LINE eKYC
特徴
コミュニケーションツール、SNSとして圧倒的な利用者数を誇るLINEが開発したeKYCソリューションです。
安全性と利便性を追求した本人確認が可能で、本人確認に係る作業の軽減を実現します。
LINEが開発した最高水準の精度のAI技術を搭載した文字認識技術、顔認識技術が搭載されており、真贋判定サポート機能が搭載されているため本人確認書類の表裏を認識や厚み撮影時に必要なカードの矩形や角度を解析することが可能です。
料金
- 初期費用:要問い合わせ
- 月額料金:要問い合わせ
※料金情報は2022年1月時点のもの
TRUSTDOCK
特徴
eKYC/KYCの分野で多くの導入数を誇るTRUSTDOCKは強固なセキュリティで安心なオンライン本人確認を可能とします。
確認業務のアウトソーシングにも対応しており、本人確認用のAPIツールも提供しています。
2名〜数万名と幅広い規模の企業で導入されており、金融業界を始め幅広い業界での導入実績があります。
初めてeKYCを導入するという方にも、これまでの導入実績を活かした手厚いサポートを提供しておりデータ分析に基づくアドバイスで入力フォームの改善などに貢献します。
料金
- 初期費用:要問い合わせ
- 月額料金:要問い合わせ
※料金情報は2022年1月時点のもの
ProTech ID Cheker
特徴
開発不要、最短1週間で導入ができるeKYCがProTech ID Chekerです。
犯罪収益移転防止法上や古物営業法、携帯電話不正防止利用法など多様な法規定に対応しています。
スマートフォンカメラでの顔写真撮影、免許証撮影、ランダム画像などによってオンライン上でオンライン本人確認を導入することができます。
認証側は対象を選択して必要な項目を確認した上で「認証する」ボタンをワンクリックするだけで認証作業が完了するため、業務負荷が大きく軽減されます。
料金
- 初期費用:要問い合わせ
- 月額料金:要問い合わせ
※料金情報は2022年1月時点のもの
LIQUID eKYC
特徴
LIQUID eKYCは、株式会社Liquidが運営しており、AIを搭載した審査により、本人確認業務の自動化を実現したeKYCです。
エンドユーザーが離脱しないよう、本人確認を安全かつスピーディーで低コストに行えるツールとして高い人気を誇ります。
誰でも簡単に利用できるのが大きな魅力で、申し込みフォームにタグを設置すればすぐに利用することが可能です。
料金
- 初期費用:30,000円
- 月額料金:50,000円
※料金情報は2022年11月時点のもの
GMO顔認証eKYC
特徴
GMO顔認証eKYCは、SSLなど、セキュリティに関して豊富なノウハウを所有する同社が提供するeKYCソリューションです。
例えば、犯罪収益移転防止法や、携帯電話不正利用防止法、金融業界)・古物営業法(リユース業界)など、関連する法律に則ったオンライン本人確認が実現されます。
導入費用はかからず、利用回数に応じて従量課金制が採用されています。
料金
初期費用:不要
料金:月額20,000円~(月50件)
※料金情報は2022年11月時点のもの
ダブルスタンダードeKYC
特徴
ダブルスタンダードeKYCは、独自のデータクレンジング技術を活用して高い精度で本人確認書類の読み取りができるサービスです。
文字情報、顔写真を正確に読み取り、真贋判定も可能で、運転免許証やマイナンバーカード、健康保険証など幅広い種類の帳票に対応しています。
また、クライアントのニーズに合わせた柔軟なカスタマイズが可能な点も魅力的です。
料金
- 初期費用:要問い合わせ
- 月額料金:要問い合わせ
※料金情報は2023年6月時点のもの
Polarify eKYC
特徴
Polarify eKYCは、Daon社の生体認証技術を活用したeKYCソリューションです。
Daon社の生体認証技術は、出入国管理や、オンラインバンキングなどで利用実績が豊富となっています。
スマートフォンアプリやWebブラウザに組み込むことで、本人確認書類と顔社員から本人確認を行うことができるようになります。
運転免許証やマイナンバーカード、在留カードなど、幅広い帳票に対応しています。
料金
- 初期費用:要問い合わせ
- 月額料金:要問い合わせ
※料金情報は2023年6月時点のもの
Deep Percept for eKYC
特徴
Deep Percept for eKYCは、Deep Percept株式会社が手掛けるeKYCサービスです。
AI技術において実績のある運営元が手掛けているため、柔軟なカスタマイズが可能な点が優れています。
専用のアプリは必要なく、Webブラウザで利用することができます。
本人確認前に、本人確認書類が本物かどうかを判定する真贋機能を搭載しているため、高い精度を実現しています。
また、個人情報の保護については、撮影画像等を保持しないで判定することができるため、情報流出のリスクが低い点が特徴的です。
料金
- 初期費用:要問い合わせ
- 月額料金:要問い合わせ
※料金情報は2023年6月時点のもの
Sumsub KYC/AML
特徴
Sumsub KYC/AMLは、sumsub社が提供しているeKYCサービスです。
海外産の製品となっており、容貌画像と本人確認書類による認証はもちろんのこと、住所やメールなど、様々な認証方法に対応しています。
これらの認証方法を組み合わせてeKYCを実施することができるため、より強固なセキュリティ対策を実施できる点が特徴的です。
料金
- 初期費用:要問い合わせ
- 月額料金:要問い合わせ
※料金情報は2023年6月時点のもの
まとめ
eKYCについて基本的な意味や導入するメリット、おすすめのサービスなどを紹介させていただきました。
スマートフォンやネットサービスの普及により本人確認が必要となる場面も多くなりましたが、それに伴いセキュリティと利便性を重視した本人確認方法も求められています。