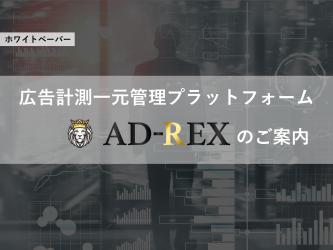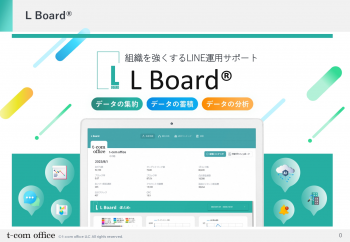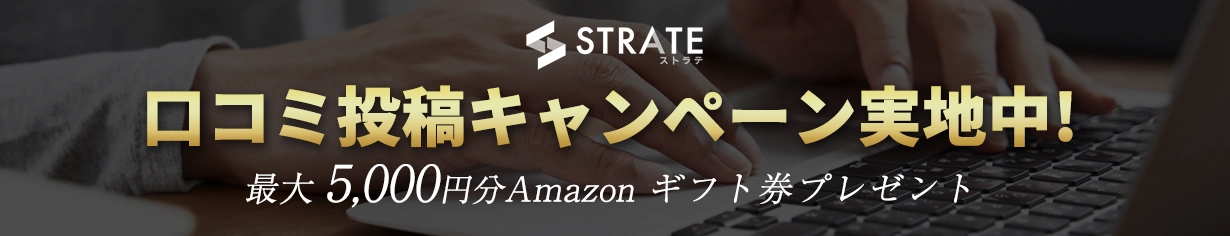CPMは、インターネットマーケティングの分野において、頻繁に登場する用語です。
CPC、CPAなど似たような用語もあることから、CPMと混同してしまう方や間違った使い方をしている方も多いようです。
このCPMは、WEB広告に携わる方にとって非常に重要な用語となりますので、正しく理解して使えるようにしておきましょう。
本記事で、CPMの意味、計算方法、類似する用語との違いなどについて、解説していきます。
また、CPM課金のメリット・デメリットについても触れていきますので、参考にしてみてください。
CPM(Cost Per Mille)の意味・わかりやすく解説

最初に、CPMがどのような意味を持つ用語なのかについて、解説します。
CPM(シーピーエム)とは?
CPMは、「Cost Per Mille」(コスト・パー・ミル)の頭文字を取った省略系です。
Costは「費用」、Perは「~につき、~ごとに」などの意味があります。
Milleは、ラテン語で「1,000」を意味する単語です。
つまり、Cost Per Milleは、日本語に訳すと、「1,000回あたりの費用」という意味になるのです。
CPM(シーピーエム)=インプレッション単価
CPMは「インプレッション単価」とも呼ばれています。
インプレッション単価は、WEB広告が1,000回表示されるごとに発生する料金のことです。
純広告、運用型広告などのWEB広告配信の指標として、よく使われることが多い用語です。
CPMと似た用語(CPC、CPA)との違い
CPMと似たような用語としては、CPC、CPAなどがあります。
どれも、似たようなアルファベットが並んでいるため、混同しないように気を付けてください。
うっかり間違えてしまうと、相手に意味が伝わらなくなることや正確な広告料金が算出できなくなってしまうおそれがあります。
CPC(シーピーシー)とは?
CPCは、「Cost Per Click」の頭文字を取った省略形です。
「クリック単価」とも呼ばれています。
WEB広告を見たユーザーが1回クリックするごとにかかる費用のことを意味する用語です。
CPCは、広告表示にかかった費用÷クリック回数で求めることができます。
CPA(シーピーエー)とは?
CPAは、「Cost Per Acquisition」の頭文字を取った省略形です。
「顧客獲得単価」とも呼ばれています。
新規顧客を獲得するにあたって、どのくらいの費用がかかるのかを示す用語です。
CPAは、「顧客獲得にかかった費用の総額÷実際に獲得した顧客の数」で求めることができます。
CPMの計算方法について
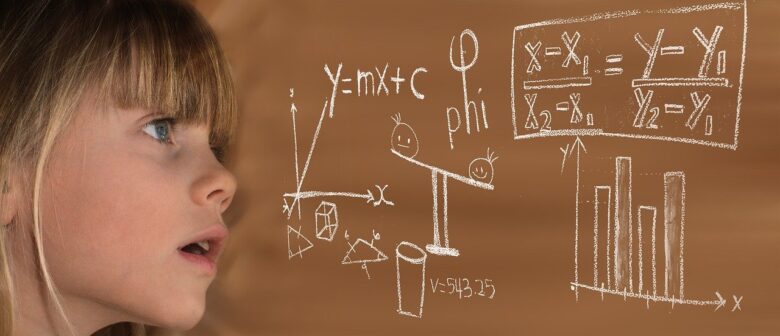
次に、CPMの計算方法について解説します。
計算というと難しいというイメージを持たれる方もいらっしゃるかもしれませんが、CPMの算出は非常に簡単です。
CPMの計算式
CPMは、以下の計算式から求めることができます。
CPM=広告掲載にかかる費用÷広告が表示された回数×1,000
たとえば、広告掲載費用が10万円、広告表示回数が20万回だったとした場合は、(100,000÷200,000)×1,000=500という計算式になります。
CPM(インプレッション単価)の額は、500円です。
もしも、広告掲載費用が10万円、広告表示回数が40万回だったとした場合は、(100,000÷400,000)×1,000=250という計算式になります。
このように広告掲載費用が同額の場合には、広告の表示回数が多ければ多いほど、単価が下っていくのがCPMの特徴です。
WEB広告におけるCPM課金(インプレッション課金)について~メリットデメリット~
WEB広告では、CPM課金(インプレッション課金)方式が用いられることが多いです。
ただ、CPM課金には、以下のようなメリット、デメリットがありますので、注意が必要です。
CPM課金のメリット

CPM課金のメリットは、以下の通りです。
クリック数に左右されない
CPM課金のメリットは、クリック数に左右されないことです。
広告がクリックされても、まったくクリックされなかったとしても、料金は一定です。
そのため、クリック数が上がりやすい広告の場合には、費用を安く抑えることが可能となります。
料金が一定なので予算が組みやすい
一定料金であるため、広告費の予算が組みやすいことも、CPM課金の良いところです。
多くのユーザーに広告を見てもらえる可能性が高い
また、CPM課金は、インプレッション数が最大になるように配信されるため、多くのユーザーの目に留まりやすいという利点もあります。
商品やサービスなどの宣伝目的で、できるだけたくさんのユーザーに見てもらいたいときには、一番おすすめの方法と言えます。
CPM課金のデメリット

CPM課金には、以下のようなデメリットもあります。
クリック率が低い場合でも一定の費用がかかる
CPM課金のデメリットは、表示回数によって課金されるシステムとなっているため、クリック率が低い場合でも、一定の費用がかかってしまうことです。
クリックされる回数が少ない広告の場合には、CPC課金を選んだほうがコストが抑えられる可能性があります。
費用対効果がわかりにくい
また、CPM課金には、成果がわかりにくいというデメリットもあります。
ユーザーがどのサイトから流入してきたのか、商品購入のきっかけなどが見えにくくなっているのです。
費用対効果をしっかりと把握したい場合には、向かない方法と言えます。
CPM課金型の広告と相性の良い施策について
最後に、CPM課金型広告と相性が良い施策をいくつかご紹介します。
大手SNSをターゲットにした広告配信する
CPM課金型広告は、ユーザーの目に触れやすいというメリットがあるため、多くのユーザーが集まるSNSとの相性が非常に良いです。
Facebook、Twitter、Instagramなど登録者数が多いSNSをターゲットにすれば、よりたくさんのユーザーへアプローチしやすくなります。
自社のブランド力、認知力を高めたいときには、CPM課金型広告はうってつけの施策と言えます。
あらかじめ十分な予算計画を立てておく
CPM課金型広告は、広告表示数が多いほど、サイトへの誘導率も上がっていきます。
クリック数に左右されることなく、一定料金であるCPM課金型広告の利点を上手に活用して、十分な予算計画を立てておくと良いでしょう。
CPMを正しく理解してコス適切なコスト管理を
以上、CPMの意味、計算方法、CPM課金型広告などについて解説いたしました。
CPMは、広告が1,000回表示される度に発生するコストのことを意味する用語です。
CPM課金型広告は、クリック数に関係なく一定の料金となっており、多くのユーザーに見てもらいやすいのが利点です。
その反面、CPM課金型広告はクリック数が少ない場合でも費用がかかってしまうことや費用対効果が把握しにくいなどのデメリットもあります。
自社のブランドの認知度を高めたいのか、それとも成約率や商品購入率を上げたいのかなど、広告配信の目的をよく考えたうえで、最適な方法を選ぶようにしてください。
もしも、判断に迷ったときは、とりあえずCPC課金型広告を選んでおき、クリック数が増えてきたら、CPM課金型広告へ切り替えるというやり方もあります。
CPM課金型広告とCPC課金型広告の特徴やメリット・デメリットをよく理解したうえで、そのときの状況に合わせた方法を選んでいくと良いでしょう。