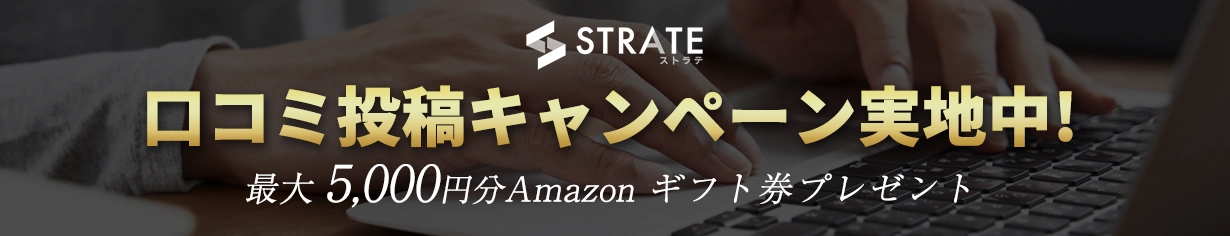労働者の裁量で働ける「裁量労働制」を導入する企業が増えてきました。
本記事では、裁量労働制に興味をお持ちの方向けに、主な特徴、メリット・デメリット、種類などについてご紹介します。
また、時間外手当、休日手当、深夜手当などの支払いが発生するのかについても触れていきますので、参考にしてみてください。
裁量労働制についてわかりやすく解説!

最初に、裁量労働制がどのような制度なのかについて解説していきます。
裁量労働制の特徴について
裁量労働制は、労働者が自分の労働時間を決定できる制度です。
会社側と労働者側で労働時間の取り決めをしておき、そのみなし時間で給料が計算されるのが特徴です。
たとえば、みなし労働時間を「8時間」と決めた場合であれば、1日の労働時間が3時間でも、9時間であっても、8時間労働したと扱われます。
業務の進め方、労働時間などを会社側が一方的に決めるのではなくて、労働者側へ任せていることが裁量労働制の大きな特徴です。
裁量労働制とフレックスタイム制の違いについて
裁量労働制は、「フレックスタイム制」と間違われることがよくあります。
確かに、両者は似ている部分もありますが、実際にはまったく異なる制度なのです。
両者を混同してしまうと、せっかく裁量労働制を導入しても、正しい運用が難しくなってしまうおそれがありますので、違いについてきちんと把握しておきましょう。
フレックスタイム制とは?
フレックスタイム制は、あらかじめ定められた総労働時間の範囲内であれば、労働者が出勤時間や・退勤時間を自由に選べる制度です。
たとえば、「朝は9時までに出社」「夕方18時になったら退社」といったように、労働者全員が一律のルールに縛られることなく働けるのがフレックスタイム制の良いところです。
このフレックスタイム制は、事務職、営業職、クリエイティブ職などが多い職場に向いていますが、工場や倉庫など労働者が一斉に仕事に取り組まなくてはならない職場では導入しにくい面があります。
おすすめの類似労務管理ツール
類似サービス: HRBrain労務管理
(4.5)
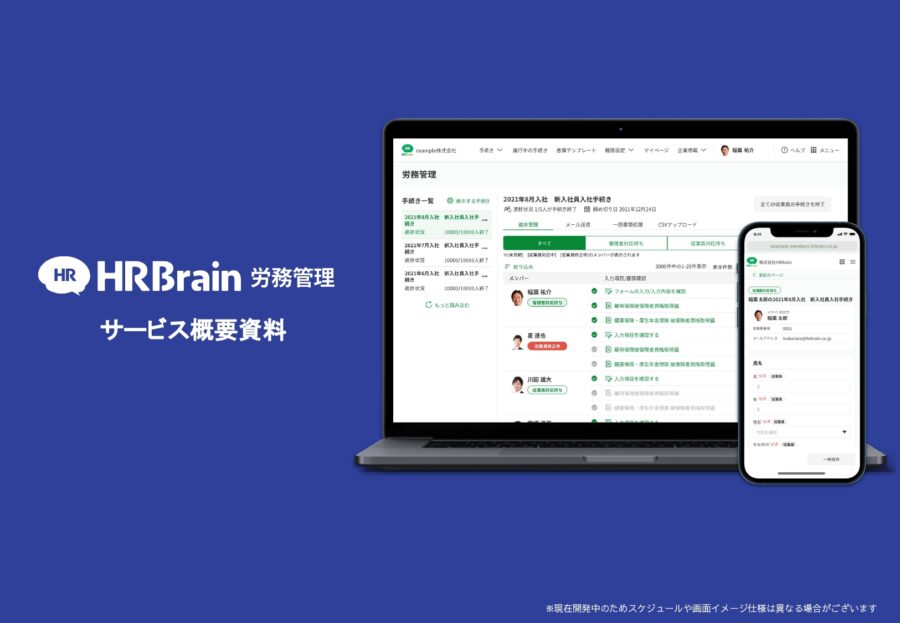
| 月額料金 | 要問い合わせ | 無料お試し | 要問い合わせ |
|---|---|---|---|
| 初期費用 | 要問い合わせ | 最短導入期間 | 1ヶ月〜2ヶ月 |
HRBrain労務管理とは、株式会社HRBrainが運営している労務管理システムです。 人事労務業務のペーパーレス化や業務効率化ができる点はもちろん、人材データの一元管理までをワンストップで実現できるとして、これまで1,000社以上をサポート※してきた実績があります。
煩雑な人事労務業務をシンプルに
HRBrain労務管理は、オンライン上で従業員データの収集や管理、更新手続きといった人事労務業務を完結することができます。 これまで時間がかかっていた入退社の手続きといった書類作成も、システム上で完結できるため、ペーパーレス化につながります。
データの一元管理までがワンストップで実現できる
HRBrain労務管理は、労務担当者だけでなく、従業員の工数も削減することができます。 従業員が入力したデータを自動で蓄積、常に最新の人材データベースを活用することが可能となります。 人事労務業務の効率化から人材データの一元管理までが、ワンストップで実現できます。
手厚いサポート体制
HRBrain労務管理は、初めて労務管理システムを導入する方はもちろん、既に利用しているサービスからの乗り換えを検討している方にもおすすめです。 初期設定や操作方法に関する懇切丁寧なサポートを提供しています。
類似サービス: 労務・給与アウトソーシング
(4.5)
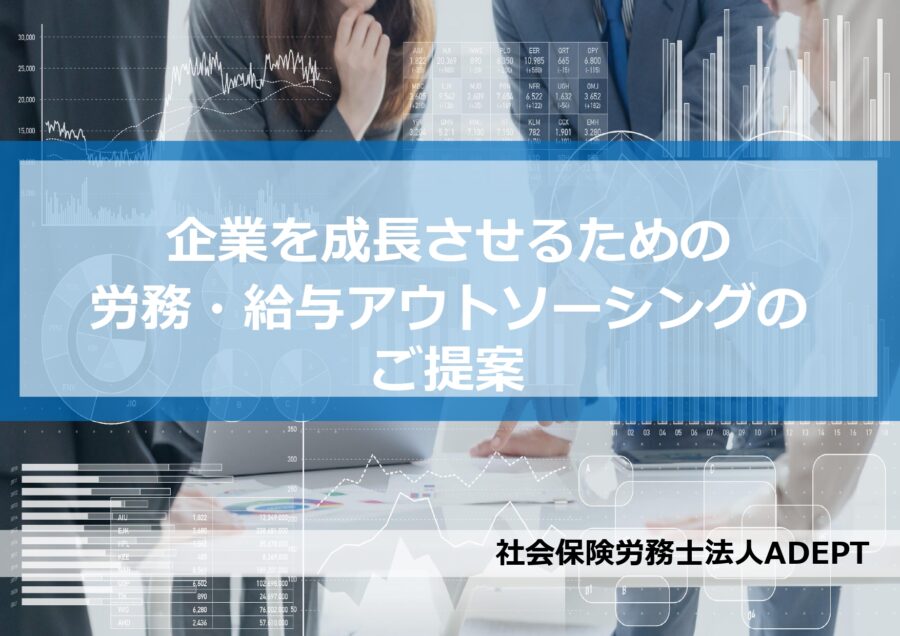
| 月額料金 | 50,000円〜 | 無料お試し | 要問い合わせ |
|---|---|---|---|
| 初期費用 | 要問い合わせ | 最短導入期間 | 要問い合わせ |
社会保険労務士法人ADEPTが展開している労務・給与アウトソーシングは、企業の実態を把握して整理、労務環境の改善を実現します。 「将来のビジョンを具体的に描いておらず、不安がある」、「労務管理における課題が明確になっていない」、「労務管理の方法がわからない」、「従業員が働きやすい環境を構築したい」といった課題を感じている方におすすめのサービスです。
課題を明確化
労務・給与アウトソーシングでは、導入企業ごとの課題を明確にするために、現状の確認・対応度の診断を行なっています。 「労働条件の通知」、「求人」、「賃金台帳」、「就業規則」、「雇用保険」のような項目に沿って質問を行い、「はい」、「いいえ」、「不明」、「対象外」といった回答をすることで、企業ごとの課題を明確にして、最適な対応を実現します。
給与管理を効率化
労務・給与アウトソーシングでは、給与関係にクラウド型の労務業務の管理サービスを利用しており、管理や更新はADEPT側で対応してくれるため、企業側に手間が発生しません。 人事担当者へIDを付与するのでいつでもリアルタイムに社員情報や賃金台帳などを閲覧してダウンロードすることができます。
豊富なオプションサービスを用意
労務・給与アウトソーシングでは、「労務顧問」、「従業員用問い合わせ窓口」、「勤怠システム導入」、「勤怠集計作業」、「勤怠チェック」のようなオプションを用意しています。 導入企業の要望に応じて柔軟に対応することが可能です。
類似サービス: freee人事労務
(4.5)
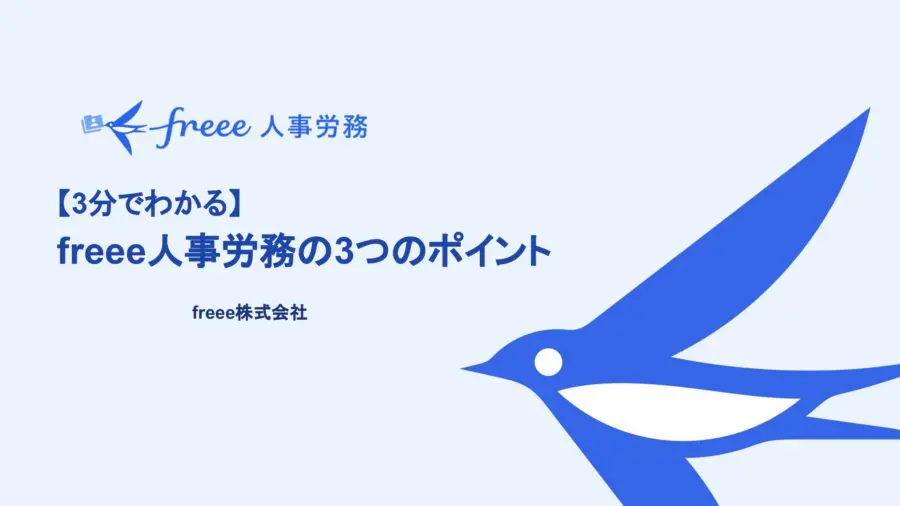
| 料金 | 年額23,760円〜 | 無料お試し | 要問い合わせ |
|---|---|---|---|
| 初期費用 | 0円 | 最低導入期間 | 1ヶ月〜 |
freee人事労務とは、freee株式会社が運営している人事・労務業務の一元管理を可能とするクラウドツールです。 年末調整や勤怠管理、給与計算機能といった労務業務を一元化することができます。
あらゆる人事情報を一元化
従来のシステムでは、業務やシステムごとにバラバラになってしまった人事情報が、freee人事労務を導入することで一元管理できるようになります。 入退社処理や身上変更によって蓄積された従業員データを勤怠申請や給与計算など、幅広い業務に活用して業務効率化を実現します。
幅広い業務をペーパーレス化
freee人事労務は、勤怠から給与計算、年末調整まで、幅広い業務のペーパーレス化を実現します。 紙でやりとりしていたものがオンラインで完結するようになるため、ペーパーレス化によるコストカットが期待できます。
業務の抜け漏れを防止
freee人事労務にはアラート機能が搭載されており、タスクを登録しておくことで抜け漏れをゼロにすることができます。 アラート通知がされることで、やるべきことが可視化されるだけでなく、イレギュラーな業務が発生した場合もfreeeがお知らせしてくれるため安心です。
「フレキシブルタイム」や「コアタイム」がある
フレックスタイム制は、「フレキシブルタイム」と「コアタイム」という2つの時間帯が設定されているのが特徴です。
フレキシブルタイムは、労働者が出勤時間や退勤時間を自分で決定できる時間帯のことです。
たとえば、フレキシブルタイムが9時~13時、16時~19時までと決められていた場合、その時間内であれば好きな時間に出勤・退勤しても問題ありません。
今日は病院へ行くので11時に出勤する、午前中に打ち合わせがあるので9時から出勤するといったように、自分の都合に合わせてスケジュールが立てやすいのが、この制度の利点です。
コアタイムは、労働者が必ず勤務する時間帯のことです。
たとえば、コアタイムが13時から17時までと決められていた場合は、その時間までに出勤して仕事を行わなくてはなりません。
無断で出勤・退勤することはできません。
裁量労働制にはこのような時間帯がありませんので、フレックスタイム制と比較して、より労働者の自由度が高い制度と言えます。
対象となる業務や職種が限定されていない
裁量労働制は、専門性職、本社勤務者を対象とした制度となっています。
一方、フレックスタイム制では、職種や業務が限定されていません。
裁量労働制と比較して制限がゆるいので、多くの企業で導入しやすい制度と言えます。
2つの裁量労働制の種類と対象者の事例
裁量労働制は、「専門業務型裁量労働制」と「企画業務型裁量労働制」の2種類があります。
また、対象者についても、法律によって具体的に定められています。
それぞれの特徴、対象者については、以下の通りです。
専門業務型裁量労働制とは
仕事の遂行や手段、労働時間の決定などを労働者の裁量に委ねる必要がある場合、法律によって定められた業務に限って認められる制度のことです。
弁護士、税理士、会計士などの専門資格職、デザイナーやコピーライターなどのクリエイティブ職、研究職など、合計19業務が専門業務型裁量労働制の対象となっています。
対象の職種については、厚生労働省のホームページ上に記載があります。
具体的な職種や業務について調べたい方は、そちらでもチェックしてみてください。
企画業務型裁量労働制とは
企画、立案、調査、分析などの特定の業務に携わるホワイトカラー職を対象とした制度です。
この制度は、本社、本店勤務など、事業の運営に重要な影響を及ぼす事業場に限られています。
工場、倉庫、支店などでは、基本的に導入ができません。
裁量労働制のメリットとデメリット
裁量労働制には、良い点だけでなく、悪い面もあります。
労働者側のメリット

裁量労働制の良い面は、労働者のペースに合わせた働き方ができることです。
労働者自身の裁量で仕事のコントロールができるので、頑張り次第で短時間労働も可能となります。
また、業務の進め方に関しても、労働者に委ねられていることから、仕事へのモチベーション、自己管理能力が高まりやすくなるといったメリットもあります。
会社側のメリット
会社側にとっては、無駄な残業時間削減、生産性アップが期待できるという利点があります。
定時出勤・定時退社という概念に縛られることなく働きたいという人が多い会社であれば、導入するメリットがある制度と言えるでしょう。
労働者側のデメリット

労働者側のデメリットは、残業代が貰えないです。
みなし労働時間が8時間と決められている場合、8時間を超える仕事をしても残業代は1円も発生しません。
残業代を稼いで生活の足しにしたいと考えている方にとっては、メリットが少ない働き方となってしまう可能があります。
また、仕事量が多い職場、仕事のペースが遅い人の場合には、長時間労働に陥りやすいデメリットもあります。
長時間労働が常態化すると、身体的にも精神的にも負担がかかり、身体を壊してしまうリスクもあるので、注意が必要です。
会社側のデメリット
会社側のデメリットは、従業員の労務管理が複雑化しやすいことです。
総務担当者、人事担当者、管理職たちの業務が増えて負担が大きくなる可能性もあります。
また、従業員の出勤や退勤時間がバラバラになることで、社員同士で顔を合わせる時間が短くなることやコミュニケーション面での支障が出るなどのデメリットもあるのです。
裁量労働制での残業代について|時間外手当、深夜手当、休日手当に関して
裁量労働制では、みなし労働時間によって給与が計算されるため、基本的には残業代が発生しません。
ただし、条件を満たしていれば、残業代が発生することもあるのです。
また、深夜手当、休日手当に関しては、通常の働き方と同様のルールでの支給対象となります。
残業代(時間外手当)が発生するケース
時間外手当が発生するのは、みなし労働時間が8時間を超えた場合です。
たとえば、みなし労働時間を10時間と設定していた場合であれば、法定労働時間の8時間を差し引いた「2時間」が時間外割増賃金支給対象となります。
裁量労働制では残業代がないと勘違いしている雇用主や従業員も意外と多いので、気を付けたほうが良いでしょう。
もしも、未払いの残業代があった場合には、後からであっても雇用主へ請求することができます。
深夜手当
22時から翌朝5時までの時間帯は、25%以上の金額を上乗せした割増賃金率が発生します。
たとえば、12時から深夜1時まで仕事をしたのであれば、3時間分が深夜手当の支給対象となります。
休日手当
休日出勤した場合も、休日手当の支給対象となります。
法定休日に勤務した場合には、割増賃金率として35%以上の金額を上乗せした賃金が発生します。
メリット·デメリットを理解して裁量労働制を導入しよう
裁量労働制は、法律職、クリエイティブ職、研究職、会計職などの専門的な業務に携わる人を対象とした制度です。
業務や職種等の制限がありますが、労働者の裁量で仕事をコントロールできる、生産性やモチベーションが高まる、残業時間削減できるといった良い点も多い制度です。
その反面、長時間労働になりやすい、労務管理が複雑になるなどのデメリットもあります。
雇用主側がきちんとした運用体制を整えていかないと、労働者側に大きな負担をかけてしまうことにもなりかねません。
導入時には、デメリット面の対処方法をきちんと考えておくことが大事なポイントとなります。