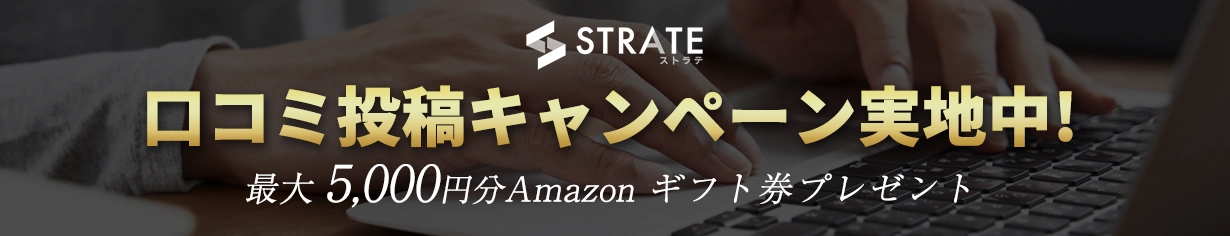様々な福利厚生を手軽に取り入れることができ、管理の手間も効率化できることから福利厚生サービスが注目されています。
しかし、せっかく導入した福利厚生がなかなか浸透せず、社内の利用率が低いとお悩みの方も多いのではないでしょうか。
本記事では、福利厚生サービスの利用率が低い原因とその対策について解説しますので参考にしてください。
福利厚生サービスの種類
福利厚生サービスは大きく分けて2種類に分類されます。
パッケージプラン
パッケージプランとは、福利代行サービス側で提供しているパッケージサービスのことを指します。
旅行先や観光内容が決まっているパッケージツアーのようなもので、様々な種類の福利厚生の中からテーマごとにコースを設定し、パッケージ化して提供されています。
導入企業側は、自社の目的や予算に合ったコースを選び、契約することで手軽に複数の福利厚生を取り入れることができます。
パッケージプランは、会員定額制となっているサービスが多く、従業員1人あたりに料金が発生します。
パッケージ化されたものを選んで契約するだけなので、手軽にまとめて福利厚生を導入することができ、運営の手間や予算が抑えられる点がパッケージプランのメリットです。
カフェテリアプラン
カフェテリアプランは、好きな食べ物を自由に選択して注文することができる「カフェテリア」が由来となっているプランで、導入企業側が自由に福利厚生制度やサービスをパッケージ化し、従業員に提供することができます。
カフェテリアプランでは、福利厚生サービスにどのような福利厚生を取り入れたいかを相談し、手配や運用に関する業務を任せることが可能です。
企業側は従業員に一定の補助金を支給し、従業員はその支給された補助金内で福利厚生を利用する形式となりますが、付与される補助金額は偏りがないため、不公平という印象を与えないこと、自分に必要な福利厚生を従業員自身で選択できる点がメリットと言えます。
おすすめの類似福利厚生サービス
社内で栄養バランスの良い食事が取れる: オフィスおかん
(5.0)

| 月額費用 | 要問い合わせ | 無料お試し | サンプルあり |
|---|---|---|---|
| 初期費用 | 要問い合わせ | 導入会社 | 累計導入実績3,000拠点以上※ ※2021年11月時点 |
職場に専用冷蔵庫とお箸やお皿など入ったボックスを設置し、電子レンジを用意するだけで手軽に開始できるオフィスコンビニ型の社食サービスです。商品はすべて1品100円(税込)※、24時間温かい食事を取ることが可能。数十名の規模の小さな拠点から利用できます。 ※100円は想定利用価格です
管理栄養士監修の美味しいお惣菜が格安で食べられる
オフィスおかんのお惣菜は、専任の管理栄養士監修の美味しくて健康的なお惣菜です。 国産食材を極力優先して使用し、添加物の使用も極力控えているため、小さなお子さんでも安心して食べることができます。 冷蔵(チルド)保存されているため、1分程度温めるだけですぐに食べることができます。また、そのまま食べられるお惣菜もあるそうで、忙しい日のランチ休憩にもぴったりです。
幅広い規模の企業に対応できる!
企業の規模に合わせた冷蔵庫が3タイプ用意されているので、自社のスペースを圧迫することもありません。自動販売機バージョンを置くことも可能です。 テレワークを導入している企業には「オフィスおかん仕送り便」がおすすめで、個人宅でもオフィスおかんの栄養バランスが考えられた惣菜を届けてもらうことができるようになります。
使い方のバリエーションが豊富
オフィスおかんは従来の社食とは違い、24時間利用することができ、ランチ以外にも早朝勤務の方の朝ごはん、夜勤や残業時の夜ご飯として使えるため、シフト勤務の企業でも導入できる点が魅力的です。
類似サービス: yui365
(4.5)

| カタログ代金 | 4,100円〜 | 無料お試し | 要問い合わせ |
|---|---|---|---|
| 初期費用 | 0円 | 最低導入期間 | 要問い合わせ |
yui365とは、株式会社yuiが運営しているデジタルカタログギフトサービスです。 数ある商品をの中から自由に組み合わせてデジタルカタログを贈ることができ、取引先はもちろん、社員への福利厚生にも活用されています。 自社のロゴや写真を盛り込むことができ、URL送付型の納品形式も用意されているため、離れた相手にも簡単にオリジナルのデジタルカタログギフトを贈ることが可能です。
メッセージ・写真・ロゴを挿入できる
yui365は、社員や取引先の好みに合わせて商品を選択し、オリジナルのデジタルカタログを作成することができます。 特徴的なのは、予め用意された商品リスト以外に、自社商品やリクエストした商品を盛り込むこともできる点です。 メッセージや写真、会社のロゴを挿入できることから、経営者から社員へ想いを届けるなど、特別な日を彩ることができます。
URL送付ですぐにギフトを贈ることができる
デジタルカタログギフトなので、URLをメールやチャットシステムで送信するだけで離れた場所にいる相手に対しても、簡単にギフトを贈ることが可能です。 さらに、QRコードを記載したギフトカードを届けることも可能なため、自社の用途や送り先に合わせて柔軟に選択することができます。
豊富なプランを用意
yui365では、5種類以上のランクプランを用意しており、用途や相手に合わせて柔軟に選択することができます。 1冊4,100円のお手頃なランクプランから、特別な日に贈りたい10,000円以上のランクプランまで用意されており、ランクプランによって掲載可能な商品が異なります。 カタログは、1冊から申し込むことができます。
類似サービス: LEBER
(4.5)

| 月額料金 | 100円〜/人 | 無料お試し | 要問い合わせ |
|---|---|---|---|
| 初期費用 | 要問い合わせ | 最短導入期間 | 要問い合わせ |
LEBERとは、CBC株式会社が運営サポートしている医療相談アプリです。 アプリを活用してお持ちのスマートフォンから、チャット形式で24時間365日医師に相談することができます。 一人あたり月額100円~で実際に医療機関に行かなくても手軽に相談ができるため、テレワークを取り入れている企業での健康経営促進にも貢献します。
手軽に問診票を作成
LEBERでは、チャットボットを活用して手軽に問診票を作成することができます。 調子の悪い箇所や症状内容などを選ぶだけという手軽さで、煩わしい操作も必要なく、短時間で問診票を作成することができるため、利用者がストレスを感じることがありません。
症状に合わせた適切なアドバイスをもらえる
LEBERは、いつでも手軽に医師へ相談することができ、最短3分で実名登録された医師からのアドバイスが得られます。 症状に応じた市販薬の推奨もしてくれるため、夜間や週末などの病院が空いていない時間帯でも自己解決することが可能となります。
日本最大級の医師ネットワーク
LEBERには、約400名の医師が登録しています。 内科や外科、産婦人科、小児科、精神科をはじめとした26診療科の医師がサポートしているため、症状に合わせたアドバイスが可能です。
福利厚生サービスの利用率が低い原因
従業員からのニーズに応える福利厚生がない
どんなに福利厚生の種類を充実させても、従業員が利用したいと思えるような福利厚生がなければ利用率は低いでしょう。
企業側が社員のためになると思って導入した福利厚生と、社員が求めている福利厚生にミスマッチがある場合、導入しても利用率が向上しないことが予想されます。
また、導入している福利厚生が一部の人しか利用できない、特定の人にのみ需要がある場合も利用率は向上しないでしょう。
例えば、旅行や保養所施設の利用とった福利厚生は、一見すると歓迎されそうですが、仕事が忙しく時間がとれない人にとっては魅力的ではないため利用されない可能性があります。
福利厚生は従業員の家族まで利用できるサービスも多いため、どのようなサービスの需要が高いのかをしっかりと検討して導入することをおすすめします。
福利厚生制度の周知が不十分
従業員が、どのような福利厚生を利用できるか知らない、というのも利用率が低い原因でしょう。
福利厚生に限らず、新しい制度やサービスを導入した際は、従業員への周知が重要となります。
掲示物として貼り出すだけでなく、メールや朝会での告知などを行い、従業員全員が福利厚生について認識している状態になることが理想的です。
制度の名前だけは知っているという可能性もあるため、どのようなサービスが利用できるのか、利用するためにはどのような手続きが必要なのかも併せて周知活動に務めましょう。
利用するための手続きが複雑
福利厚生制度の存在は知られていても、利用するための手続きが複雑である場合、利用率の向上は期待できないでしょう。
福利厚生を利用するたびに申請書を作成したり、添付書類が必要になったりすると、サービスを利用する意欲がなくなってしまいます。
気軽に利用することができるように、なるべく簡素化された利用方法を確立することが利用率を高めるためには有効です。
福利厚生サービスの利用率を上げる方法
従業員のニーズが高い福利厚生を取り入れる
福利厚生サービスの利用率を高めるためには、どのような福利厚生を従業員が求めているのかを理解することが重要です。
そのため、まずはどのような福利厚生が人気かをしっかりと調査しましょう。
社内アンケートを活用し従業員のニーズを調査、福利厚生の導入後にもアンケートをとることで満足度を把握することができます。
福利厚生の内容を知らせる
福利厚生サービスの認知度を高めることで、利用率の向上が期待できます。
そのため、まずはオフィスに掲示物として福利厚生の内容をお知らせしたり、メールで周知したりといった方法で広報活動を行いましょう。
従業員に福利厚生の内容が周知されるまで、定期的に告知を行うことが重要です。
利用率を改善させる福利厚生サービスの選び方
従業員が利用しやすいサービスを選ぶ
全ての従業員が普段から利用しやすいサービスを選びましょう。
利用する機会が少ないサービスや日常的に利用しにくいサポートは利用率の低下につながります。
従業員へのアンケートを行い、ニーズを把握した上でサービスを導入すると良いでしょう。
簡単な手続きで利用できるサービスを選ぶ
福利厚生の利用率を高めるためにも利用しやすいサービスを選ぶことが重要です。
複雑な手続きなくサービスや施設の利用を申し込むことができるサービスであれば、自ずと利用率も高まるでしょう。
スマートフォンやパソコンから申し込みができると、より手軽に利用することが可能です。
福利厚生サービスの利用率を高めよう
福利厚生サービスの利用率について解説しました。
福利厚生サービスの利用率が低下している場合は、低下している要因を明確にし、対策を講じることが重要です。
本記事で紹介した対策方法も参考にして、ぜひ利用率の向上に務めてください。