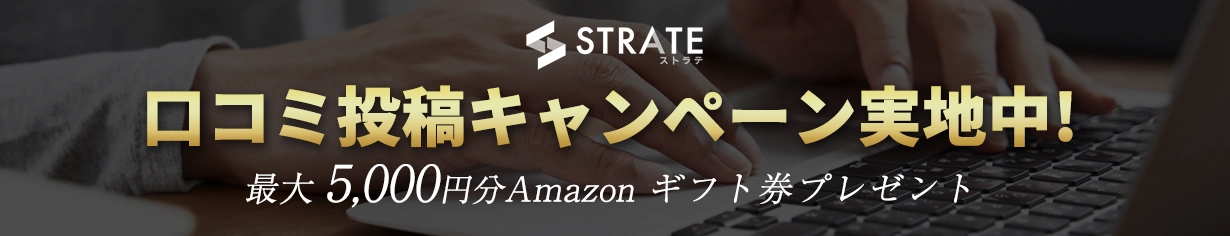減価償却とは会計知識であり、経営者にとっては重要な項目です。
仕訳や計算にたくさんのルールがあり、難しく感じるのも事実ですが、メリットもあるのでしっかり理解することが大切です。
実施した場合は貸借対照表や損益計算書への記載も必要となりますが、ここでは減価償却に関する基礎知識や計算方法、メリットデメリットなどを解説します。
減価償却とは?概要と目的をわかりやすく解説

減価償却とは、会計処理の一つであり、固定資産の購入費用を分割して計上する方法です。
企業が事業を行ううえで必要とする設備や機械装置はさまざまありますが、その購入費用を、使える期間で分けて経費計上していくやり方になります。
たとえば、固定資産に該当するパソコンを例に取ると、購入時には最新機種でも、年月とともに古くなることでその価値も減少し、最終的には資産価値の認められないものになります。
このように資産価値が下がっていくものを減価償却資産と言い、購入費用はそのパソコンを使用できる期間で分割し、経費計上しなければなりません。
原則、購入年度に一括で経費計上することはできず、決められた年数に分けて処理していくことになります。
類似サービス: ジョブカン会計
(4.5)
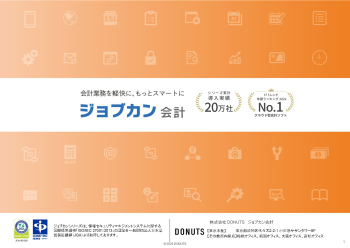
| 月額料金 | 2,500円~ | 無料お試し | 30日間 |
|---|---|---|---|
| 初期費用 | 0円 | 導入社数 | 20万社以上 |
ジョブカン会計とは、ジョブカン勤怠管理をはじめとする「ジョブカンシリーズ」を提供する株式会社DONUTSが運営しているクラウド型会計ソフトです。 操作性に優れ、会計業務の多くを自動化できる利便性の高さが評価され、多くの企業に導入されています。
操作性に優れている
ジョブカン会計は、デスクトップ版に近い親しみやすいデザインで設計されており、直感的な操作で利用することができます。 基本的な操作はキーボードで簡潔、手入力が必要な場面でも簡単に入力することが可能です。
集計作業を効率化
ジョブカン会計には、自動集計機能が搭載されており、入力した仕訳から自動で各種集計を作成してくれます。 これまで担当者が帳簿へ転記していた手間や時間を削減することができ、少人数での会計業務を実現します。
内部統制を強化
ジョブカン会計では、内部統制の強化を実現する柔軟な権限設定が可能となっています。 社内の会計情報を閲覧・編集できる人材や範囲を柔軟に設定することができます。
類似サービス: freee会計
(4.5)

| 月額料金 | 1,980円~ | 無料お試し | 30日間 |
|---|---|---|---|
| 初期費用 | 0円 | 導入社数 | 要お問合せ |
freee会計とは、freee株式会社が運営しているクラウド会計ソフトです。 インボイス制度や電子帳簿保存法に完全対応しており、煩雑な経理業務の効率化を実現します。 有料利用中のユーザーは、33万社を突破、クラウド会計ソフトシェアNo. 1※の実績があります。
法改正に完全対応
freee会計は、インボイス制度や電子帳簿保存法に完全対応しています。 クラウド型のサービスとなっているため、法改正に対してソフト側が自動でアップデートして対応することができ、企業側で設定を変更する手間がかかりません。
仕訳作業を効率化
freee会計は、全国ほぼ全ての銀行と連携対応済みで、同期した銀行口座やクレジットカードの明細をもとに、帳簿付けすることができます。 明細からの転記作業、仕訳入力が全て自動化できるため、経理担当者の負担を大きく軽減することが可能です。
ボタンを押すだけで決済書を作成
小規模企業などでは、税理士などに依頼するコストを削減して、自社だけで決算申告をしたいという場合もあります。 経理や簿記の知識がないので、自社だけで決算申告ができるか不安という方にこそ、freee会計はおすすめです。
会計ソフトをお探しの方におすすめの関連サービス
類似サービス: SUPPORT+iA
(4.5)

| 月額料金 | 75,000円〜 | 無料お試し | 要問い合わせ |
|---|---|---|---|
| 初期費用 | 要問い合わせ | 最低契約期間 | 要問い合わせ |
SUPPORT+iAとは、グランサーズ株式会社が運営しているオンラインアシスタント・秘書サービスです。 企業のバックオフィス業務を丸ごとアウトソーシングすることができ、公認会計士/税理士といった有資格者によって業務監修されているため、確かなサービス品質が約束されています。
バックオフィス業務を丸ごとアウトソーシング
SUPPORT+iAでは、幅広いバックオフィス業務を依頼することができ、人材不足を解消してコア業務に集中できるようになります。「庶務」「財務」「経理」「人事・労務」といったバックオフィス業務を「ネット×リアル」の対応によってカバーすることが可能です。
厳しい審査を突破した正社員が対応
SUPPORT+iAでは、サービスを提供するのは全て正社員に限定しています。 SUPPORT+iAの正社員は、採用率1%未満という厳しい採用過程を突破した人材で、研修や検定試験といった徹底した社員研修を受けており、バックオフィス業務に対する豊富な専門性を有している点が特徴的です。
低コストから運用できる
オンラインアシスタントの費用相場は、月額5万円〜10万円程度と言われています。 SUPPORT+iAでは、1ヶ月75,000円/15時間稼働から利用できる4つのプランを提供しているため、利用企業の業務量に応じた最適な料金で導入することが可能です。
類似サービス: 「楽楽明細」
(4.5)

| 月額費用 | 要問合わせ | 無料お試し | トライアル環境あり |
|---|---|---|---|
| 初期費用 | 要問合わせ | 導入会社 | 8,000社超 |
請求書処理の完全ペーパーレス化を実現する請求書の代行受領・データ化サービス。紙・メール・PDF等形式を問わず、取引先から届くすべての請求書を一律で代行受領してくれます。
あらゆる帳票発行の自動化が可能
「楽楽明細」は、請求書や納品書、支払い明細、領収書といったあらゆる帳票の電子化、自動発行が可能です。 帳票データを楽楽明細へ取り込むだけでWebか郵送、メール添付、FAXのいずれかの方法の中から、顧客に応じて自動で割り振り発行してくれるため、書類発行における印刷や封入作業などの手間が大きく効率化されます。
とにかく簡単&シンプル
新しいシステムを導入すると、操作を覚えるために学習期間が必要となることがネックですが、楽楽明細は初めてシステムを利用する方でも直感的に理解できる操作性のため、実際に操作しながら覚えることができます。 請求書発行業務に特化した機能が搭載されており、余計な機能がないため、「機能が多すぎて使いこなせない」という課題は発生しません。
契約継続率99%を実現するサポート体制
「楽楽明細」では、導入から実際の運用までを懇切丁寧にサポートしてくれます。無理に契約するようなことはなく、他社比較をした上で納得して契約することが可能です。 幅広い業界の帳票電子化をサポートしてきた経験があるため、業界特有の課題にも対応することができます。
類似サービス: ジョブカン会計
(4.5)
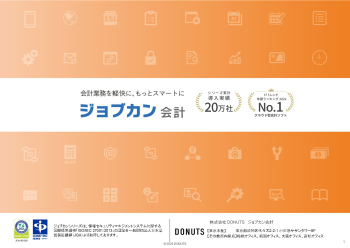
| 月額料金 | 2,500円~ | 無料お試し | 30日間 |
|---|---|---|---|
| 初期費用 | 0円 | 導入社数 | 20万社以上 |
ジョブカン会計とは、ジョブカン勤怠管理をはじめとする「ジョブカンシリーズ」を提供する株式会社DONUTSが運営しているクラウド型会計ソフトです。 操作性に優れ、会計業務の多くを自動化できる利便性の高さが評価され、多くの企業に導入されています。
操作性に優れている
ジョブカン会計は、デスクトップ版に近い親しみやすいデザインで設計されており、直感的な操作で利用することができます。 基本的な操作はキーボードで簡潔、手入力が必要な場面でも簡単に入力することが可能です。
集計作業を効率化
ジョブカン会計には、自動集計機能が搭載されており、入力した仕訳から自動で各種集計を作成してくれます。 これまで担当者が帳簿へ転記していた手間や時間を削減することができ、少人数での会計業務を実現します。
内部統制を強化
ジョブカン会計では、内部統制の強化を実現する柔軟な権限設定が可能となっています。 社内の会計情報を閲覧・編集できる人材や範囲を柔軟に設定することができます。
減価償却できる資産とできない資産がある
減価償却となるものにはルールがあり、固定資産すべてが該当するわけではありません。
減価償却できる資産とできない資産とを解説します。
減価償却できる資産
- 業務に使用するもので取得価額10万円以上のもの
- 時間の経過とともに資産価値が減少する固定資産
- 使用可能な期間が1年以上であるもの
- 有形か無形かは問わない
まず業務に使用するもので、取得価額10万円以上のものであることが大前提です。
そのうえで、前述した通り時間の経過とともに資産価値が減少する固定資産を対象としますが、使用可能な期間が1年以上である必要があります。
有形か無形かは関係なく、建物や工具なども該当しますし、ソフトウェアや特許権などの権利関係も該当します。
また家畜や樹木なども該当しますので、生産農家や酪農家も減価償却できる対象は少なくありません。
減価償却できない資産
- 時間の経過で資産価値が減少しないものは対象としない
- 土地や借用権は対象外
- 美術品や骨董品も対象外
用途が業務に使っていないものは当然のことながら、資産価値が時間の経過で減少しないものは該当しません。
たとえば土地は景気変動はあっても資産価値が年々下がるものではないため該当しませんし、借用権などの無形資産も減価償却資産ではありません。
美術品や骨董品も該当せず、減価償却対象とはならないので覚えておきましょう。
また建設中の建物は、そもそもまだ固定資産として計上ができないので除外です。
建物は、竣工して実際に使用が開始されてから減価償却することになります。
施工前や施工途中段階で建設代金を支払うと、金額は建設仮勘定として固定資産に計上することができますが、その時点では減価償却の対象にはならないので注意しましょう。
ほかには、棚卸し資産は対象外となります。
これらは実際に販売したときに売上原価として費用計上するのが正解です。
状態によって判断が分かれる場合も
- 未使用の資産や稼働休止中の資産などは減価償却対象外
- 休止期間中に維持補修が実施されている場合は減価償却の対象になる場合も
該当するのは業務に使っているものというのが前提ですが、設備など稼働しているかしていないかで状況が変わる場合があります。
基本的に未使用の資産、稼働休止中の資産などは減価償却対象外となるのですが、休止期間中に維持補修が実施されていると減価償却資産に該当することになります。
たとえば、なんらかの製品を製造するための生産設備が今現在は稼働していないとしても、メンテナンスを行い、いつでも稼働ができる状態にあるものは減価償却対象です。
つまりスタンバイ状態は休止とはみなされませんので、そこは覚えておきましょう。
減価償却費の会計上の仕訳方法と計算方法

減価償却は、仕訳に「直接法」と「間接法」の2種類が、計算に「定額法」と「定率法」の2種類があります。
それぞれ正しく理解することが重要です。
仕訳方法2種類
それではまず仕訳方法の2種類をそれぞれまとめておきましょう。
直接法
減価償却費を固定資産から直接差し引きます。
現在の固定資産の価値が一目でわかります。
間接法
固定資産は減らさず減価償却累計額を計上します。
取得原価と償却額の合計がわかります。
原則、無形固定資産には直接法が用いられ、有形固定資産には間接法が用いられます。
計算方法2種類
計算方法はそれぞれ以下の内容です。
定額法
減価償却費=取得価額×定額法の償却率
毎年一定額を経費計上するため、償却費は毎年同額です。(期の途中購入の場合はその年だけ月割り)
帳簿がシンプルでわかりやすいので資産計画が立てやすいでしょう。
定率法
減価償却費=未償却残高(購入年度は取得価額)×定率法償却率
毎年一定の割合で経費計上します。
償却保証額を下回った場合は「改定取得額×改定償却率」が減価償却費となります。
結果的に初年度が減価償却費が一番大きくなり、早く資産償却ができるでしょう。
定額法であれ定率法であれ、償却率は耐用年数ごとに定められています。
主な償却率は国税庁のホームページにも掲載されていますが、固定資産の取得年によっても率が異なるので注意が必要です。
減価償却で大切な「耐用年数」
耐用年数は税法で決められていますが、種類ごとに非常に細かく定められており、改正も行われます。
会計処理では年度ごとに耐用年数のチェックが非常に重要であり、税制法の改正も含めて随時確認が必要です。
また、青色申告書の中小企業や個人事業主、農業協同組合などの組織を対象に特例があり、30万円未満の減価償却資産は合計限度額300万円を上限に、一括計上ができます。
こうしたルールを細かく調べ、正しく処理ができるようにすることが重要です。
耐用年数表に関しては、国税庁の確定申告書等作成コーナーの「よくある質問」からもアクセスできます。
国税庁ホームページ
減価償却するメリット·デメリットや注意点
減価償却は、所得税を納めている個人事業主は必ず行う義務があります。
ただ法人税法上、法人は任意となっており減価償却をしなくても違法ではありません。
ですが、非常に多くの企業が当然のごとく実施していることからもわかるように、減価償却費の計上にはメリットがあります。
具体的にどのようなメリットがあるか見ていきましょう。
メリット

節税効果
高額の資産を購入した場合、減価償却しなければその年だけ多額の経費が計上され、翌年以降は利益のみが大きくなります。
つまり翌年からは法人税をたくさん納付しなければならないことになり、大変不利です。
減価償却すれば、償却期間中は法人税額を抑えることができる分、節税効果を生むことになります。
キャッシュフロー向上
ずっと経費を計上するということは、償却期間中、経理上の利益は減ります。
ただ実際にお金が出ていっているわけではありませんので、費用計上した分はキャッシュフローとして手元に残せることになります。
もちろん見かけ上の社内留保ですが、数字上、財務状況を良くすることができます。
経営状態把握
減価償却することで、購入した資産が事業収益にどれだけ貢献できているかを正しく把握することができます。
業績が実態に近づくことは企業にとって大きなメリットであり、損益を正しく把握したうえで質の高い事業計画を立てることができるでしょう。
デメリット

会計処理が複雑
減価償却は税制上ではデメリットと言える点は見当たりませんが、会計処理ではデメリットと言える部分があります。
減価償却では税制法などが改定された際には、都度合わせる必要があるため、耐用年数が改定された際には資産を多く持っている企業は大きな手間が発生してしまいます。
必然的に会計処理も複雑になってしまう場合ももちろんあります。
とはいえ、システムによって税法の改定などにも自動的に対応してくれるものも登場しているので、大きなデメリットとは言えませんが、自社だけで対応している場合は手間と感じてしまうケースもあるでしょう。
知っておいて損はない減価償却
減価償却は、それぞれの資産の耐用年数や取得価額の整理など、手間がかかる処理であることは否めません。
ただ企業にとってメリットの大きい処理であり、現実的には労力を理由に実施しないという選択肢はないでしょう。
難しい場合は資産に応じた減価償却費を自動計算してくれるツールやサービスなどの活用も検討し、適切に減価償却できる体制を整えることが重要です。