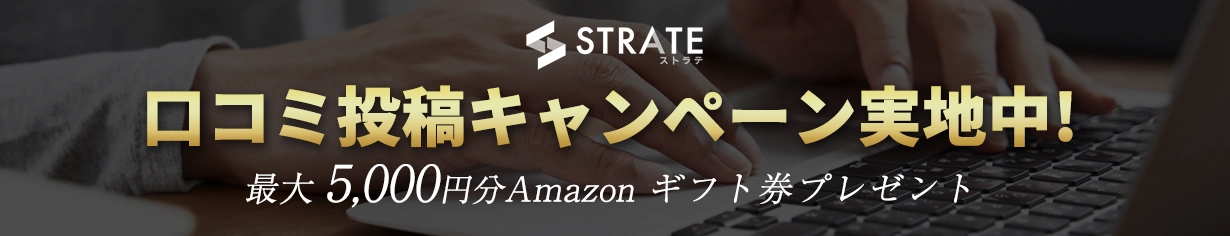レベニューシェアという契約形態をご存知でしょうか。
まだ実際にビジネスシーンにおいてレベニューシェアという言葉を聞いたことがないという方でも今後、特に経営者の方であれば耳にする機会が増えるかもしれません。
本記事ではレベニューシェアについて、基本的な意味やレベニューシェア契約を行うメリット、デメリット、レベニューシェアの配分比率の相場などを解説しますので参考にしてください。
レベニューシェアとは?
レベニューシェアとは、収益分配型の成果報酬型契約のことを指します。レベニュー(revenue)は収益、シェア(share)は分け合うと訳すことができます。
レベニューシェアはIT関係のビジネスにおいて用いられる機会が多く、Webサイト制作やシステム開発などではレベニューシェア契約を採用する企業が増えています。
特徴として、開発者側が費用を負担してWebサイトやシステムなどの成果品を開発、その後成果品から発生した収益を予め決めておいた割合で分配する点が挙げられます。
プロフィットシェアとの違い
レベニューシェアと混同されがちなのがプロフィットシェアです。
レベニューシェアは、事業によって得た収益を予め決めておいた割合で分配する方式を指します。
一方でプロフィットシェアは事業で得た収益から「経費」を差し引いた利益を分配する方式になります。
両者の違いとしては収益を分配するか、利益を分配するかという対象が違いますが、どちらも成果報酬型の契約ではあります。
レベニューシェアが活用されるようになった背景
従来の契約方式では依頼者からの発注内容に応じてシステムなどの開発を行い、対価として報酬を支払う買い切り型が一般的でした。
ですが、買い切り型は依頼する側の費用負担が大きく実際に完成したシステムを動かしてみるまでは効果がわからない点も問題となっていました。
レベニューシェアであれば開発者側が費用を負担するため、依頼者側は初期投資にかかるコストを抑えることができ、コストをかけることができない中小企業でもシステム開発やWebサイト制作を依頼しやすくなりビジネスチャンスを広げることができるため採用される機会が増えています。
レベニューシェアのメリットとデメリット
レベニューシェアのメリット
レベニューシェア契約のメリットとしては主に以下の点が挙げられます。
- 受注者は継続的に収益を受け取ることができる
- 発注者は初期投資コストを抑えて仕事を依頼しやすくなる
- 受注者側のモチベーション維持につながる
- 決まった分配率以上の支払いがなくなる
レベニューシェア契約は、受注側(開発側)が収益の分配や保守などの報酬を長期的、継続的に得られることがメリットです。従来の買い切り型の契約では決めた範囲内での報酬を得たら終わりという形式が多いのに対して、レベニューシェア契約はこの点が違います。
事業の収益が増えれば必然的に分配される報酬も増えることとなるため、モチベーション維持にもつながるためこの点もメリットと言えるでしょう。
発注者側も従来であれば最初にまとめて支払わなければいけなかった初期費用を抑えることができるため、リスクを軽減できるというメリットがあります。
また、初期リスクが低くなるため仕事を依頼しやすくなることから、受注者側にとっては成約率が高まるというメリットも生まれます。
レベニューシェアのデメリット
レベニューシェア契約のデメリットとしては以下の点が挙げられます。
- 収益が増えるほどに支払う報酬も高くなる
- ビジネスがうまくいかなった場合は双方の利益が少なくなる
- 契約内容を詳細に決めておかないとトラブル時の責任の所在が曖昧になる
決まった分配比率において報酬を継続的に支払うこととなるため、発注者側はビジネスの収益が増えるほどに報酬として支払う金額も高額になることに注意が必要です。
また、レベニューシェア契約において、ビジネスがうまくいかなかった場合、受注者側は初期費用を負担しているためデメリットが大きくなります。
その他にも、依頼された仕事の内容に対しての報酬が見合っていない、ビジネスが失敗した原因を押し付けられるといったトラブルが起きてしまう可能性もあるため契約内容は詳細に決めておく必要があります。
レベニューシェア契約を成功させるには、両者で納得した上で慎重に契約内容を確認して信頼関係を築くことが重要でしょう。
レベニューシェアの配分比率の相場
レベニューシェアの配分比率は契約時に依頼者側と開発側双方で相談の上決められます。
報酬の配分比率には特別な決まりはなく、事業内容や収益率などの条件によって都度異なります。
しかし、レベニューシェアは受注側(開発側)が費用負担をするためリスクが高いため、固定報酬の契約と比較して高額になるように配分比率を決めることが多いです。
また、収益の分配だけではなく月額費用を受注者に支払うケースや、開発者側の負担が大きい段階では配分比率を高くして初期費用が回収できた後に配分比率を変更するといったケースもあります。
レベニューシェア契約書の作る上での注意点
レベニューシェア契約をする上で契約書の作成には細心の注意が必要です。
契約後のトラブルを避けるという意味でも依頼者側と開発者側とで役割分担をしっかりとしておきましょう。
契約時に決めておくべき項目の一例としては以下が挙げられます。
- 分配の比率
- 契約の目的
- 業務分担の範囲
- 費用負担の割合
- 成果物の著作権や知的財産権の帰属先
- 分配金支払いの対象期間
- システムの利用者や保守管理者
- セキュリティトラブル時の対応
- 契約期間
- 契約終了に関するルール
上記以外にも依頼内容や依頼側•開発側の特徴に合わせて項目を細かく決めておくと、トラブルを回避することができます。
レベニューシェアの成功事例
レベニューシェア契約は幅広い分野で取り入れられるようになっていますが、その代表的な事例を紹介します。
あべのハルカス
大阪の新しい名所として有名な超高層ビル「あべのハルカス」を運営する近畿日本鉄道は美術館の入退場管理システムの構築においてパナソニックISとレベニューシェア契約を結びました。
開発者側であるパナソニックISは入場者ゲートや発券端末などのシステム開発を行い、あべのハルカス側はチケットの発券数を基準として報酬を支払います。
レベニューシェア契約によってあべのハルカス側は初期投資のコストや運用にかかる負担を軽減することができ、パナソニックIS側はクラウドでサービスを提供することでリスクの低下を実現しています。
ECサイトの事例
通販サイトでは、サイト制作者と運営者の間でレベニューシェア契約が行われるケースが増えています。
サイトをリリースしてから実際に商品が売れることによって収益が上がりますが、この収益をサイト運営者と開発者側で分配する契約を行うことで、サイトでの売り上げが上がるほどに運営者と開発者が得られる利益も大きくなります。
レベニューシェア契約を成功させるためには双方の信頼が重要
レベニューシェア(レベニューシェア契約)について、基本的な意味や導入するメリット•デメリット、代表的な事例などを紹介しました。
レベニューシェア契約は依頼者にとっても開発側にとってもメリットが大きいためぜひとも取り入れたい手法ですが、前提として契約内容を細部まで決めて両者の信頼関係を築くことが重要となります。
本記事で紹介したメリットやデメリットも参考にしつつ、レベニューシェアについて一度検討してみてはいかがでしょうか。