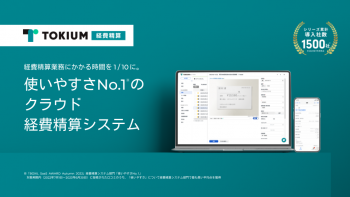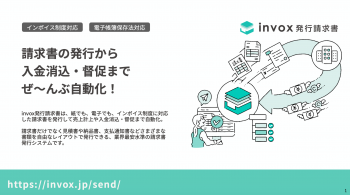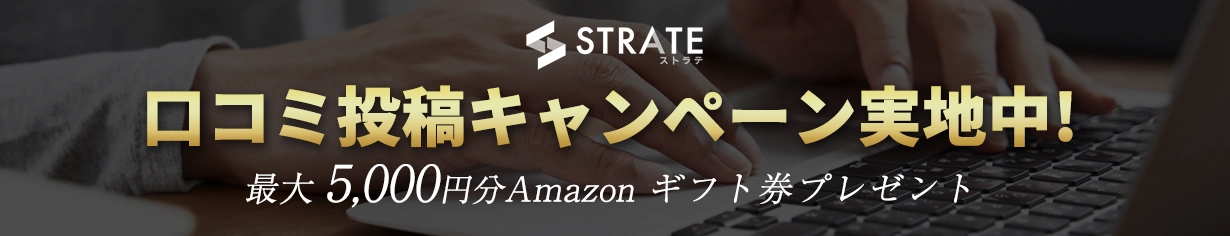帳票は、ビジネスを行ううえで必ず取り扱う書類です。
帳簿や伝票との違いがわからないという方も意外と多いのではないでしょうか?
本記事で、帳票がどんなものなのか、帳票の種類、適切な管理方法などをご紹介いたします。
また、近年、導入する企業が増えている電子帳票についても、触れていきます。
どんな電子帳票ツールを選んだら良いのか知りたいという方も、本記事を参考にしてみてください。
おすすめの類似請求管理システム
類似サービス: 「楽楽明細」
(4.5)
_商材ロゴカラー.png)
| 月額費用 | 要問合わせ | 無料お試し | トライアル環境あり |
|---|---|---|---|
| 初期費用 | 要問合わせ | 導入会社 | 8,000社超 |
請求書処理の完全ペーパーレス化を実現する請求書の代行受領・データ化サービス。紙・メール・PDF等形式を問わず、取引先から届くすべての請求書を一律で代行受領してくれます。
あらゆる帳票発行の自動化が可能
「楽楽明細」は、請求書や納品書、支払い明細、領収書といったあらゆる帳票の電子化、自動発行が可能です。 帳票データを楽楽明細へ取り込むだけでWebか郵送、メール添付、FAXのいずれかの方法の中から、顧客に応じて自動で割り振り発行してくれるため、書類発行における印刷や封入作業などの手間が大きく効率化されます。
とにかく簡単&シンプル
新しいシステムを導入すると、操作を覚えるために学習期間が必要となることがネックですが、「楽楽明細」は初めてシステムを利用する方でも直感的に理解できる操作性のため、実際に操作しながら覚えることができます。 請求書発行業務に特化した機能が搭載されており、余計な機能がないため、「機能が多すぎて使いこなせない」という課題は発生しません。
契約継続率99%を実現するサポート体制
「楽楽明細」では、導入から実際の運用までを懇切丁寧にサポートしてくれます。無理に契約するようなことはなく、他社比較をした上で納得して契約することが可能です。 幅広い業界の帳票電子化をサポートしてきた経験があるため、業界特有の課題にも対応することができます。
類似サービス: Bill One
(4.5)
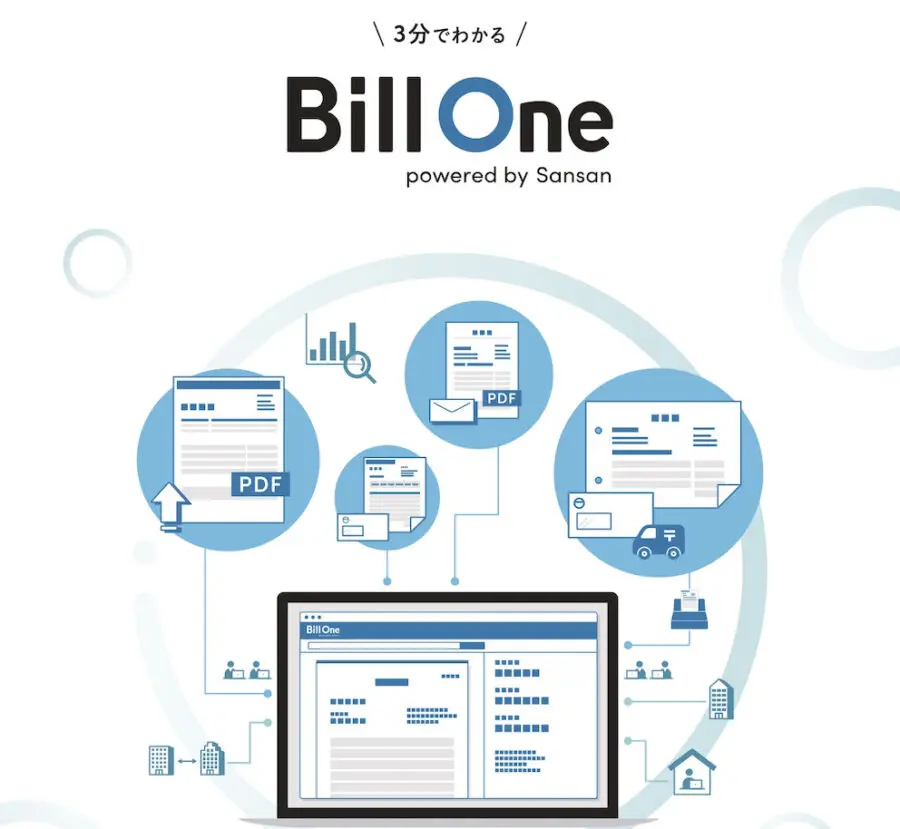
| 月額料金 | 0円〜 | 無料お試し | 要問い合わせ |
|---|---|---|---|
| 初期費用 | 0円〜 | 最短導入期間 | 1営業日から |
Bill Oneとは、Sansan株式会社が提供している請求書管理システムです。 あらゆる請求書をオンラインで受け取ることができ、法改正にも対応。自社で業務フローを変更する手間がかかりません。 拠点や部門ごとにバラバラの形式で届いていた請求書をデータ化して、経理部門を含めた会社全体の請求書業務を効率化、月次決算業務を加速させます。
どのような請求書も電子化可能
Bill Oneは、紙の請求書もPDF形式の請求書もオンラインで受け取ることができるため、請求書の発行元に負担をかけずにオンライン上で受領することが可能です。 請求書を発行する企業は、Bill Oneスキャンセンターへの郵送、専用アドレスへのメール添付、PDF形式でのアップロード、いずれかの方法で送るだけで請求書を電子化することができます。
業務フローを変えずに法改正に対応
電子帳簿保存法やインボイス制度によって、企業は要件に対応した形式での請求書保管を求められています。 Bill Oneでは、適格請求書の発行や登録番号の照合といった機能で、法改正によって求められる要件などに都度対応。導入企業側で業務フローを変更する必要がありません。
外部サービスとの連携でさらに効率化
Bill Oneでは、会計ソフトウエアをはじめとした様々なサービスとの連携によって、請求書に関連する業務をさらに効率化することができます。連携可能なサービスは、今後さらに拡大する予定です
類似サービス: SmartDeal
(4.5)
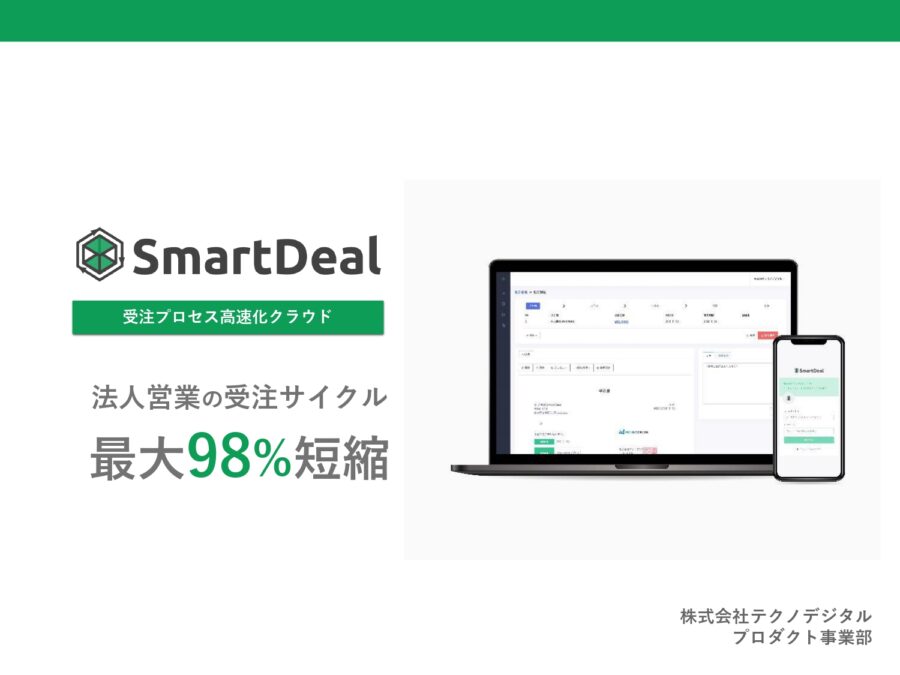
| 月額費用 | 要問い合わせ | 無料お試し | 要問い合わせ |
|---|---|---|---|
| 初期費用 | 要問い合わせ | 最短導入期間 | 要問い合わせ |
SmartDealとは、株式会社テクノデジタルが運営している受注プロセスの高速化を実現するクラウドサービスです。 「決裁者の外出やテレワークによる承認の遅れ」、「書類管理の煩雑化」、「発注・申込作業の遅れ」といった課題を解消し、営業プロセスを短縮することができます。
見積り管理を効率化
SmartDealには、見積りページの作成や編集が可能な機能が搭載されています。 見積りページを作成することで、クライアントが全ての見積り情報・見積書を手軽に確認できるようになります。
書類内容の確認が容易に
SmartDealを導入することで、URLから簡単に書類内容の確認ができるようになります。PC、スマートフォンから確認ができるため、出先やテレワークでの書類チェックのスピードが向上します。 書類内容の修正時にURLを変更する必要がないため、ファイル管理における煩雑化も起きません。
発注・申込もWebで完結
発注や申込がオンラインで完結できるようになるため、営業プロセスの短縮を実現します。 発注側の顧客がSmartDealを利用する上で、ユーザー登録は必要ないため、無駄な作業も発生しません。
帳票とは?わかりやすく解説します

最初に、帳票が一体どんなものなのかについてご紹介いたします。
帳票(ちょうひょう)
帳票は、帳簿や伝票などのことを指している会計用語です。
また、帳票は証拠として使う記録という意味もあります。
商品の納品、金銭の請求など、実際に行われる取引の証拠となる重要な書類のことを指しているのです。
帳簿や伝票との違い
帳票と似たような言葉としては、「帳簿」や「伝票」などがあります。
帳票の字をよく見ればわかることですが、帳簿の「帳」、伝票の「票」が漢字が含まれています。
つまり、帳票は、帳簿や伝票を組み合わせた用語なのです。
帳簿や伝票を包括したものが、帳票だと理解しておくと良いでしょう。
帳票の主な種類について
次に、帳票の種類についてご紹介します。
帳票は大きく分けると、「帳簿」、「伝票」、「証憑」の3種類があります。
それぞれの特徴について、さらに詳しく見ていきましょう。
帳簿(ちょうぼ)
帳簿は、主に会社の経営状況を把握するための書類のことです。
取引の内容、お金の流れなどを記録して残しておくために用いられています。
ちなみに帳簿は、「主要簿」と「補助簿」の2種類があります。
主要簿は、総勘定元帳、仕訳帳、日記帳の3つです。
補助簿の種類については、以下の通りです。
- 現金出納帳
- 預金出納帳
- 売掛帳
- 買掛帳
- 受取手形記入帳
- 支払手形記入帳
- 売上帳
- 仕入帳
- 固定資産台帳
伝票(でんぴょう)
伝票は、お金に関する書類のことです。
主に、入出金記録の管理の際に用いられています。
伝票の種類としては、以下のものがあります。
- 売上伝票
- 仕入伝票
- 入金伝票
- 振替伝票
- 出金伝票
証憑(しょうひょう)
証憑は、取引が行われたことを証明する書類です。
証憑の種類としては、以下のものがあります。
- 領収書
- 納品書
- レシート
- 契約書
- 賃貸借契約票
- 出勤簿
帳票の管理方法・保存期間について

法律によって、帳票には適切な管理方法が定められています。
また、保存期間も決められているため、勝手に処分することはできません。
もしもいい加減な帳簿管理をしていた場合には、ペナルティを受けることもあるので注意してください。
帳票の管理方法は「紙」が原則
帳票の管理は、「紙」で保存するのが原則とされています。
パソコンなどで作成した帳票であっても、プリントアウトして保管しておかなくてはなりません。
紙での保管はファイリングや保管場所の確保など管理の手間がかかってしまいますが、通信障害や情報漏えいなどのリスクが少ないのが利点です。
帳票は電子データでも保管可能
帳票は、電子データで保管しておくことも可能です。
2005年の電子帳簿保存法の改正によって、スキャンした書類の保管が認められるようになりました。
紙での保管だと必要な帳票を探すのに苦労することや保管場所に困るなども問題があることから、近年は電子データで帳票を管理する企業が増えている状況です。
電子帳票については、後の項目で解説いたします。
帳票の保存期間
会社法や法人税法などの法律によって、帳簿には7年~10年間の保存期間が設けられています。
保存期間については、帳簿の種類によって異なります。
契約書、貸借対照表、領収書、請求書などは、7年間の保管が義務付けられているのです。
現金出納帳、総勘定元帳、売掛金元帳、買掛金元帳、仕入帳などの帳簿類については、10年間保管しておかなくてなりません。
国税庁のホームページで確認しておく
帳簿の保存期間、保存方法については、国税庁の公式サイトにも記載があります。
詳しい情報を知りたい方は、こちらサイトへアクセスしてチェックしてみると良いでしょう。
電子帳票について|ツール紹介と選び方を解説
近年は、電子帳票を導入する企業が増えてきました。
項目ごとに、電子帳票がどんなものなのか、おすすめのツール、選び方についてご紹介いたします。
電子帳票とは?
電子帳票は、パソコン、専用のスキャナ―などを使って電子データ化された帳票のことです。
帳票を電子データ化することで、ペーパーレス化に対応できる、一元管理ができる、保管場所を圧迫しないなど、さまざまなメリットが得られます。
おすすめ電子帳票ツール
電子帳票ツールはいろいろなものがあります。
中でも導入実績が多いのは、FiBridgeII(ファイブリッジ ツー)です。
FiBridgeIIは、JFEシステムズ株式会社が提供している電子帳票システムです。
13年連続シェアNO.1の実績があり、さまざまな業界で導入されています。
FiBridgeIIの特徴は、高速変換・高速検索が可能なことです。
簡単な操作のみで帳票が電子化できるため、ストレスなく扱えるうえに、業務効率化も目指せます。
また、FiBridgeIIには、強固なセキュリティシステムも搭載されています。
金融系など厳格な情報管理が求められる企業にもおすすめです。
電子帳票ツールの選び方
帳票は、とても重要な書類です。
外部へ情報が漏れるのを防ぐためにも、セキュリティ対策がしっかりしているツールを選ぶようにしましょう。
電子帳票を導入する際には、社内での不正対策にも気を付けなくてはなりません。
改ざんなどを防ぐためには、ユーザーごとにアクセス権限や機能制限が設定できるツールを導入しておくのがおすすめです。
大量の帳票を取り扱う予定の場合は、使い勝手の良い帳票検索システムが搭載されているツールを選んでみると良いでしょう。
帳票と関わりが深いe-文書法について解説
帳票を取り扱う際には、e-文書法についても理解しておかなくてはなりません。
e-文書法は、帳票を電子データで保存できるように定められている法律です。
正式な名称は、「民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律」、「民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」と言います。
省略して、電子文書法とも呼ばれることもあります。
e-文書法と電子帳簿保存法との違い
e-文書法と似たような法律としては、電子帳簿保存法があります。
両者の大きな違いは、対象となる書類の範囲です。
e-文書法では基本的に法定保存文書全般が対象となりますが、電子帳簿保存法では、国税庁管轄の国税関係帳簿書類のみが対象となっています。
e-文書法のほうが対象範囲が広いと覚えておくと良いでしょう。
正しい意味を理解して帳票管理を
以上、帳票の種類、保存期間などの管理方法などについてご紹介しました。
帳票は、紙、もしくは、電子データ形式で一定期間保管しておかなくてはなりません。
ただ、紙での管理は大変な手間がかかるため、電子帳票にしておくのが便利です。
電子帳票を扱う際には、e-文書法や電子帳簿保存法など法律に関する理解も必要です。
電子帳票の導入をお考えの方は、本記事でおすすめしたツールの活用も検討してみてください。