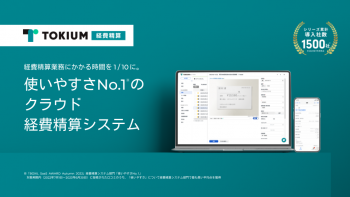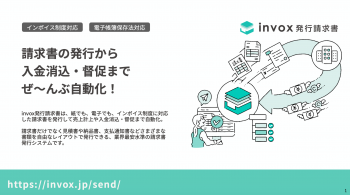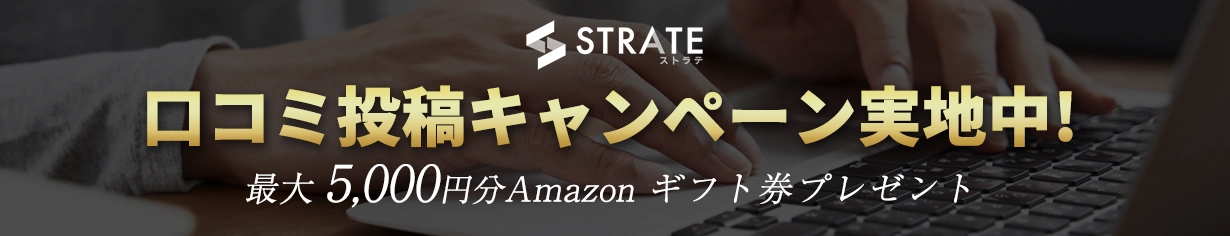2023年、新たにインボイス制度はインボイス(適格請求書)を発行することにより、取引におけて正確な消費税額を売り手に伝えるための制度です。ただしこれに対応するためには国税庁にインボイス発行事業者の登録申請が必要となります。
ではこのインボイス制度にはいつまでに、どのような方法で登録すればよいのでしょうか。
インボイス制度の登録はいつまでに必要?
インボイス制度の開始は2023年10月1日です。また登録を受け、適格請求書発行事業者となるためには、原則、2023年3月31日までに申請をおこなわなければなりません。ただし、2022年12月23日に発表された政府の「2023年度税制改正大綱」において、実質2023年9月までの延期が決定しています。
また、国税庁発出の文書によれば、登録完了までにe-Taxでは約3週間、書面であれば1ヵ月半程度時間を要するとされています。このため現状では実質的にe-Taxで2023年9月頃、書面であれば2023年8月までには申請が必要といえます。
おすすめの類似請求管理システム
類似サービス: 「楽楽明細」
(4.5)
_商材ロゴカラー.png)
| 月額費用 | 要問合わせ | 無料お試し | トライアル環境あり |
|---|---|---|---|
| 初期費用 | 要問合わせ | 導入会社 | 8,000社超 |
請求書処理の完全ペーパーレス化を実現する請求書の代行受領・データ化サービス。紙・メール・PDF等形式を問わず、取引先から届くすべての請求書を一律で代行受領してくれます。
あらゆる帳票発行の自動化が可能
「楽楽明細」は、請求書や納品書、支払い明細、領収書といったあらゆる帳票の電子化、自動発行が可能です。 帳票データを楽楽明細へ取り込むだけでWebか郵送、メール添付、FAXのいずれかの方法の中から、顧客に応じて自動で割り振り発行してくれるため、書類発行における印刷や封入作業などの手間が大きく効率化されます。
とにかく簡単&シンプル
新しいシステムを導入すると、操作を覚えるために学習期間が必要となることがネックですが、「楽楽明細」は初めてシステムを利用する方でも直感的に理解できる操作性のため、実際に操作しながら覚えることができます。 請求書発行業務に特化した機能が搭載されており、余計な機能がないため、「機能が多すぎて使いこなせない」という課題は発生しません。
契約継続率99%を実現するサポート体制
「楽楽明細」では、導入から実際の運用までを懇切丁寧にサポートしてくれます。無理に契約するようなことはなく、他社比較をした上で納得して契約することが可能です。 幅広い業界の帳票電子化をサポートしてきた経験があるため、業界特有の課題にも対応することができます。
類似サービス: Bill One
(4.5)
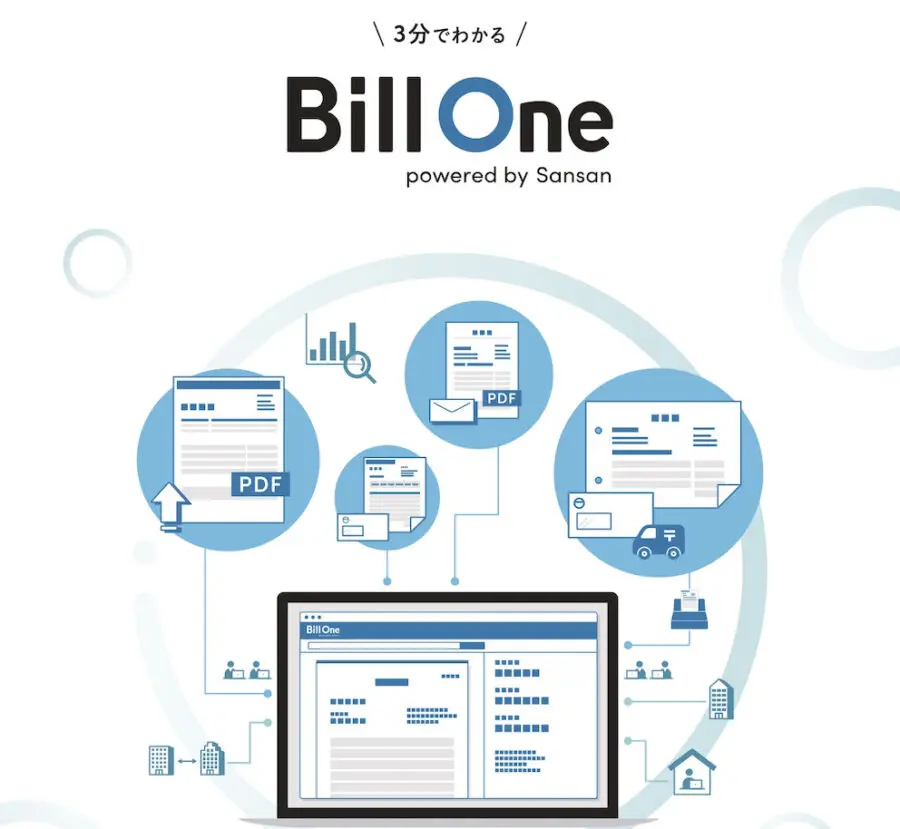
| 月額料金 | 0円〜 | 無料お試し | 要問い合わせ |
|---|---|---|---|
| 初期費用 | 0円〜 | 最短導入期間 | 1営業日から |
Bill Oneとは、Sansan株式会社が提供している請求書管理システムです。 あらゆる請求書をオンラインで受け取ることができ、法改正にも対応。自社で業務フローを変更する手間がかかりません。 拠点や部門ごとにバラバラの形式で届いていた請求書をデータ化して、経理部門を含めた会社全体の請求書業務を効率化、月次決算業務を加速させます。
どのような請求書も電子化可能
Bill Oneは、紙の請求書もPDF形式の請求書もオンラインで受け取ることができるため、請求書の発行元に負担をかけずにオンライン上で受領することが可能です。 請求書を発行する企業は、Bill Oneスキャンセンターへの郵送、専用アドレスへのメール添付、PDF形式でのアップロード、いずれかの方法で送るだけで請求書を電子化することができます。
業務フローを変えずに法改正に対応
電子帳簿保存法やインボイス制度によって、企業は要件に対応した形式での請求書保管を求められています。 Bill Oneでは、適格請求書の発行や登録番号の照合といった機能で、法改正によって求められる要件などに都度対応。導入企業側で業務フローを変更する必要がありません。
外部サービスとの連携でさらに効率化
Bill Oneでは、会計ソフトウエアをはじめとした様々なサービスとの連携によって、請求書に関連する業務をさらに効率化することができます。連携可能なサービスは、今後さらに拡大する予定です
類似サービス: SmartDeal
(4.5)
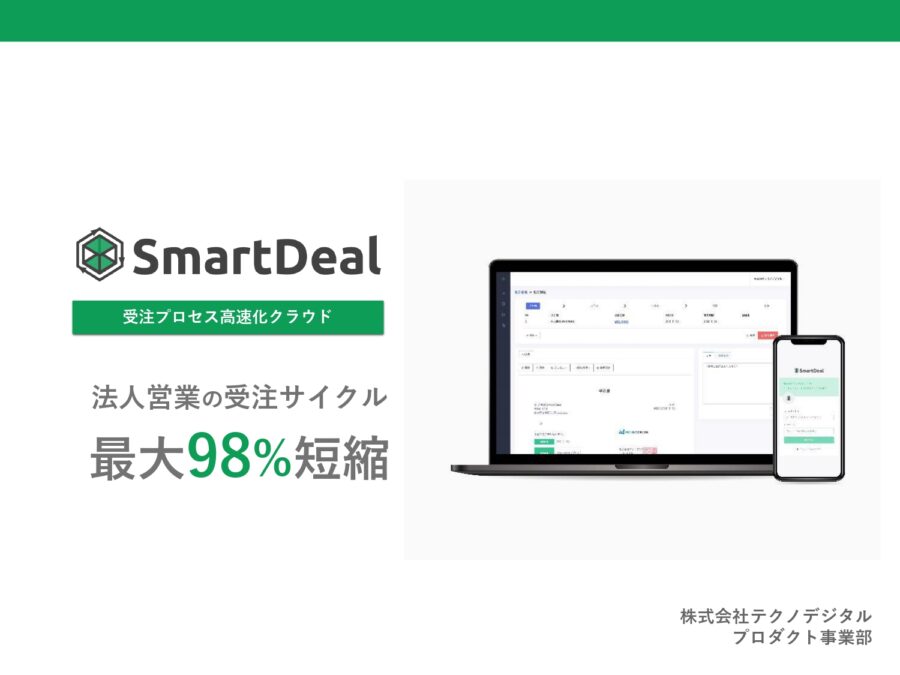
| 月額費用 | 要問い合わせ | 無料お試し | 要問い合わせ |
|---|---|---|---|
| 初期費用 | 要問い合わせ | 最短導入期間 | 要問い合わせ |
SmartDealとは、株式会社テクノデジタルが運営している受注プロセスの高速化を実現するクラウドサービスです。 「決裁者の外出やテレワークによる承認の遅れ」、「書類管理の煩雑化」、「発注・申込作業の遅れ」といった課題を解消し、営業プロセスを短縮することができます。
見積り管理を効率化
SmartDealには、見積りページの作成や編集が可能な機能が搭載されています。 見積りページを作成することで、クライアントが全ての見積り情報・見積書を手軽に確認できるようになります。
書類内容の確認が容易に
SmartDealを導入することで、URLから簡単に書類内容の確認ができるようになります。PC、スマートフォンから確認ができるため、出先やテレワークでの書類チェックのスピードが向上します。 書類内容の修正時にURLを変更する必要がないため、ファイル管理における煩雑化も起きません。
発注・申込もWebで完結
発注や申込がオンラインで完結できるようになるため、営業プロセスの短縮を実現します。 発注側の顧客がSmartDealを利用する上で、ユーザー登録は必要ないため、無駄な作業も発生しません。
インボイス制度へ登録しないとどうなる?
適格請求書発行事業者としてインボイス制度に対応するためには登録が必要ですが、必ずしもすべての事業者が登録しなければならないわけではありません。現状、消費税が免税となっている事業者であれば、インボイス制度に登録をおこなわなくてもこれまでどおり事業を継続は可能です。これを消費税免税事業者といい、課税売上高が1,000万円以下の事業者が該当します。
しかしながらインボイス制度が開始されると、適格請求書発行事業者でない場合、消費税を算出する際に課税売上の消費税額から課税仕入れの消費税額を差し引くことができる仕入税額控除ができません。すると、取引先が適格請求書発行事業者だった場合、消費税の納税負担が増加してしまうことになります。すると、インボイス制度に対応していない事業者は取引を敬遠され、事業の継続が困難になる恐れがあります。
ただし、一方で適格請求書発行事業者となり消費税の納付義務が生じると、これまでの売上の一部について消費税分として納付しなければならないため、資金繰りが悪化することも懸念されます。
このため、インボイス制度への対応にあたっては、取引先の状況を把握など、慎重に検討を進めることが重要です。
おすすめのクラウド(Web)請求書発行システム
インボイス制度登録申請に必要な手続き
検討の上、インボイス制度への登録を申請する場合には次のような手順でおこないます。
申請書類の作成
申請にあたっては、まず適格請求書発行事業者となるための登録申請書類を作成します。基本的には「適格請求書発行事業者の登録申請書」のみの作成となります。ただし、消費税免税事業者の場合には適格請求書発行事業者となるための「消費税課税事業者選択届出書」の作成も併せて必要です。
申請書類の提出
作成した書類は以下のような方法で国税庁に提出します。
郵送…管轄の国税局に郵送で送付します。管轄先でない国税局に送付してしまうと申請に時間を要してしまうため注意が必要です。
税務署へ提出…作成した書類は最寄りの税務署へ直接提出してもかまいません。
e-Tax…確定申告などで利用できるe-Taxもインボイス制度への登録に利用できます。ただしe-Taxの場合には申請書類の作成段階からe-taxにログインしてオンライン上でおこないます。また申請にはマイナンバーカードと利用者識別番号が必要となります。
取引先への通知
申請書類の提出後、審査に通過すると登録番号が届き、インボイスの発行が可能となります。その段階で登録番号や交付や受領方法と併せて取引先に通知します。また取引先がインボイス制度に対応しているかについても確認をおこないます。
インボイス制度の経過措置はいつまで?
インボイス制度には消費税免税事業者などにとって大きな影響を及ぼす施策であることから、激変緩和措置として経過措置が設けられています。その内容は、適格請求書を発行できない消費税免税事業者やインボイス制度への登録をおこなっていない課税事業者などの請求書についても、インボイス制度導入後6年間一定割合が仕入額から税額控除を受けられるというものです。
この経過措置では適格請求書発行事業者以外の仕入れに関する税額控除が以下の期間と割合で控除可能です。
- 2023年10月1日~2026年9月30日まで…仕入れ税額の80%
- 2026年10月1日~2029年9月30日まで…仕入れ税額の50%
ただし、経過措置の適用を受けるには請求書に次の4点を記載しなければあなりません。
- 課税仕入れにおける取引先の氏名あるいは名称
- 課税仕入れをおこなった日時
- 課税仕入れが資産あるいは役務の名称、経過措置の適用を受けるための課税仕入れであること
- 課税仕入れによって発生した支払い額
まとめ
インボイス制度への登録はそれほど煩雑なものではありませんが、消費税の取扱いや業務にも大きな影響を及ぼします。このため、インボイス制度への対応を進める場合には取引先の動向なども見極めながら、業務の負担増なども考慮し、適切な機能を備えた会計システムへの改変や新規導入なども併せて検討しておく必要があります。