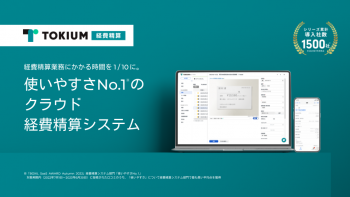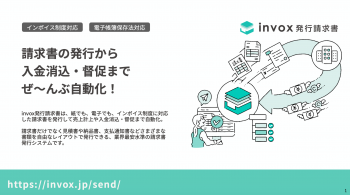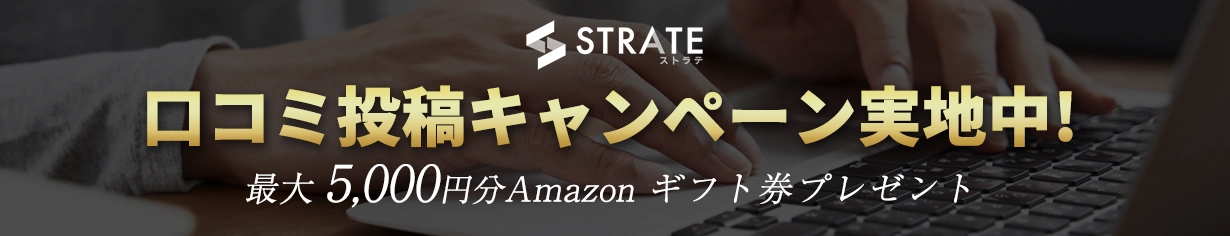紙の請求書は紛失や劣化のリスクがあるため、電子化して保存する流れが一般的になりつつあります。
取引において、電子化した請求書を用いるケースも増えていますが、もし相手先に拒否されてしまった場合はどうすれば良いのでしょうか。
本記事では、電子化した請求書について、必要性や拒否された場合などについて解説しますので参考にしてください。
請求書の電子化は必須?
2022年の電子帳簿保存法改正によって、2024年からは電子でやり取りされた取引情報は、電子データでの保存が義務付けられるようになります。
そのため、これまでは電子データを紙に印刷して保存していたという企業も、電子データの保存要件を満たした形式で保管する必要があります。
この規定については、法人はもちろん、個人事業主も対象となるため、業種や企業規模に関わらず請求書を電子化しなければいけません。
電子帳簿保存法の改正自体は2022年1月に施行されていますが、やむを得ない事情などがあり、電子化の対応が間に合わない事業者に対しては、2023年12月末までの猶予期間が設けられています。
書類の保存方法
改正電子帳簿保存法における書類の保存方法は、書類の種類ごとに異なります。
自身が電子データとして作成した帳簿や書類は、電子保存でも紙の保存にも対応しています。
ここで言う書類は、総勘定元帳や仕訳帳といった国税関係帳簿などが当てはまります。
見積書や請求書の場合は紙か電子データのうち、どちらか任意の方法で保存することが可能です。
電子データとして作成した見積書や請求書を取引先にデータとして送信した場合、書類の控えを電子データとして保存しなければいけません。Excelで作成したデータをPDF化して、メールに添付して送付した場合などが該当します。
取引の相手先から電子データとして受領した書類も電子保存する必要があります。受け渡しの方法は限定されませんので、メールやクラウドなど柔軟に選択できます。
取引先から紙で受け取った書類に関しては、そのまま紙としてファイリングして保管するか、スキャンで電子化して保存するかを選ぶことができ、電子データとして保存する場合には、スキャナ保存の要件を満たす必要があるため注意しましょう。
おすすめの類似請求管理システム
類似サービス: 「楽楽明細」
(4.5)
_商材ロゴカラー.png)
| 月額費用 | 要問合わせ | 無料お試し | トライアル環境あり |
|---|---|---|---|
| 初期費用 | 要問合わせ | 導入会社 | 8,000社超 |
請求書処理の完全ペーパーレス化を実現する請求書の代行受領・データ化サービス。紙・メール・PDF等形式を問わず、取引先から届くすべての請求書を一律で代行受領してくれます。
あらゆる帳票発行の自動化が可能
「楽楽明細」は、請求書や納品書、支払い明細、領収書といったあらゆる帳票の電子化、自動発行が可能です。 帳票データを楽楽明細へ取り込むだけでWebか郵送、メール添付、FAXのいずれかの方法の中から、顧客に応じて自動で割り振り発行してくれるため、書類発行における印刷や封入作業などの手間が大きく効率化されます。
とにかく簡単&シンプル
新しいシステムを導入すると、操作を覚えるために学習期間が必要となることがネックですが、「楽楽明細」は初めてシステムを利用する方でも直感的に理解できる操作性のため、実際に操作しながら覚えることができます。 請求書発行業務に特化した機能が搭載されており、余計な機能がないため、「機能が多すぎて使いこなせない」という課題は発生しません。
契約継続率99%を実現するサポート体制
「楽楽明細」では、導入から実際の運用までを懇切丁寧にサポートしてくれます。無理に契約するようなことはなく、他社比較をした上で納得して契約することが可能です。 幅広い業界の帳票電子化をサポートしてきた経験があるため、業界特有の課題にも対応することができます。
類似サービス: Bill One
(4.5)
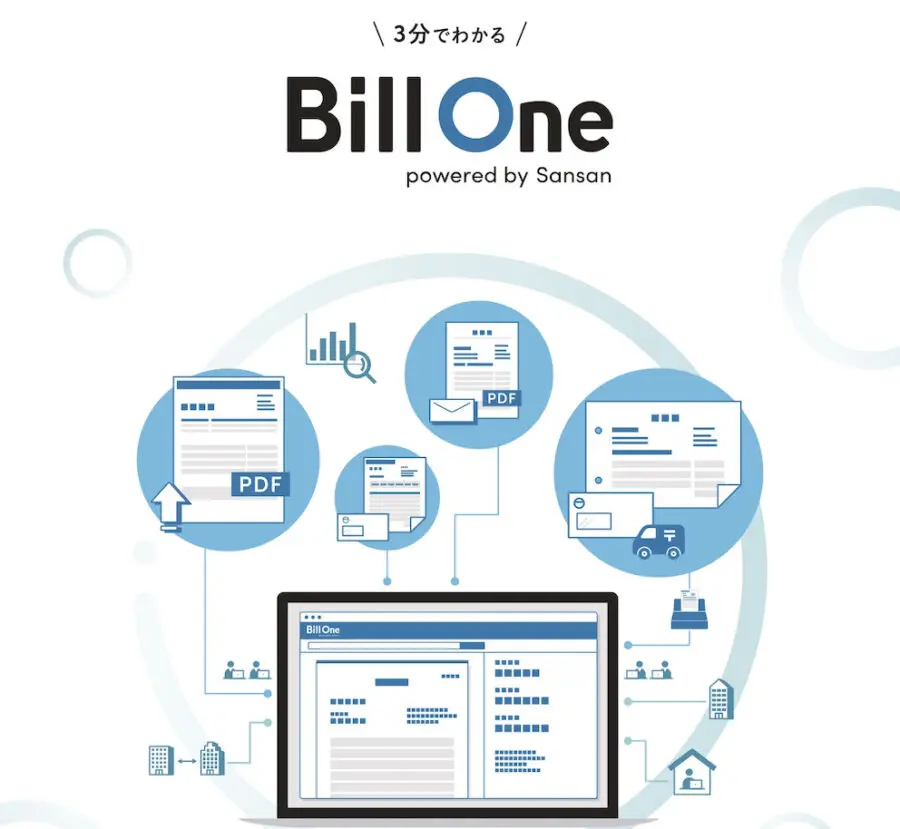
| 月額料金 | 0円〜 | 無料お試し | 要問い合わせ |
|---|---|---|---|
| 初期費用 | 0円〜 | 最短導入期間 | 1営業日から |
Bill Oneとは、Sansan株式会社が提供している請求書管理システムです。 あらゆる請求書をオンラインで受け取ることができ、法改正にも対応。自社で業務フローを変更する手間がかかりません。 拠点や部門ごとにバラバラの形式で届いていた請求書をデータ化して、経理部門を含めた会社全体の請求書業務を効率化、月次決算業務を加速させます。
どのような請求書も電子化可能
Bill Oneは、紙の請求書もPDF形式の請求書もオンラインで受け取ることができるため、請求書の発行元に負担をかけずにオンライン上で受領することが可能です。 請求書を発行する企業は、Bill Oneスキャンセンターへの郵送、専用アドレスへのメール添付、PDF形式でのアップロード、いずれかの方法で送るだけで請求書を電子化することができます。
業務フローを変えずに法改正に対応
電子帳簿保存法やインボイス制度によって、企業は要件に対応した形式での請求書保管を求められています。 Bill Oneでは、適格請求書の発行や登録番号の照合といった機能で、法改正によって求められる要件などに都度対応。導入企業側で業務フローを変更する必要がありません。
外部サービスとの連携でさらに効率化
Bill Oneでは、会計ソフトウエアをはじめとした様々なサービスとの連携によって、請求書に関連する業務をさらに効率化することができます。連携可能なサービスは、今後さらに拡大する予定です
類似サービス: SmartDeal
(4.5)
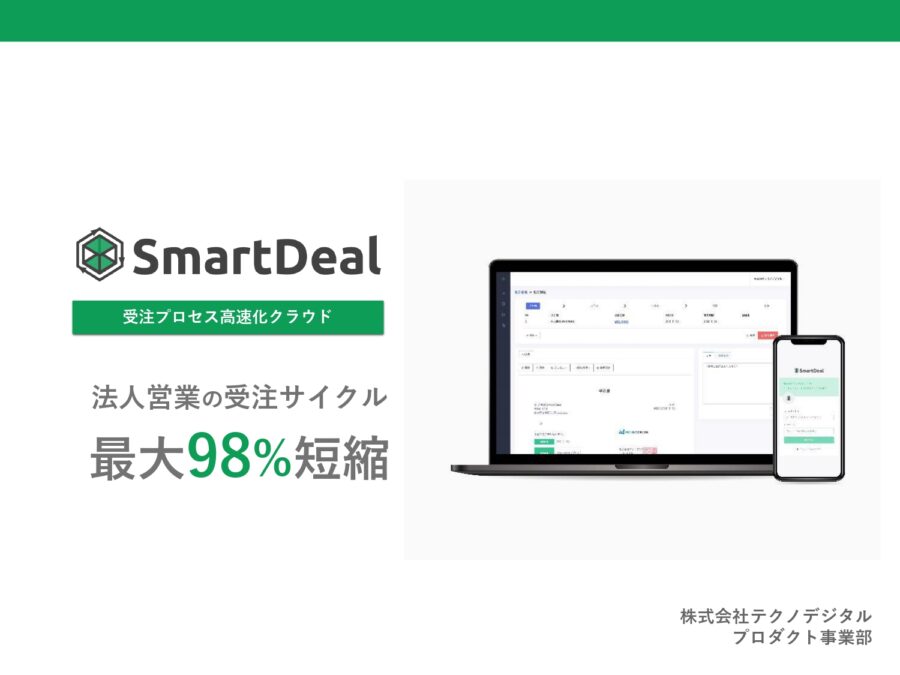
| 月額費用 | 要問い合わせ | 無料お試し | 要問い合わせ |
|---|---|---|---|
| 初期費用 | 要問い合わせ | 最短導入期間 | 要問い合わせ |
SmartDealとは、株式会社テクノデジタルが運営している受注プロセスの高速化を実現するクラウドサービスです。 「決裁者の外出やテレワークによる承認の遅れ」、「書類管理の煩雑化」、「発注・申込作業の遅れ」といった課題を解消し、営業プロセスを短縮することができます。
見積り管理を効率化
SmartDealには、見積りページの作成や編集が可能な機能が搭載されています。 見積りページを作成することで、クライアントが全ての見積り情報・見積書を手軽に確認できるようになります。
書類内容の確認が容易に
SmartDealを導入することで、URLから簡単に書類内容の確認ができるようになります。PC、スマートフォンから確認ができるため、出先やテレワークでの書類チェックのスピードが向上します。 書類内容の修正時にURLを変更する必要がないため、ファイル管理における煩雑化も起きません。
発注・申込もWebで完結
発注や申込がオンラインで完結できるようになるため、営業プロセスの短縮を実現します。 発注側の顧客がSmartDealを利用する上で、ユーザー登録は必要ないため、無駄な作業も発生しません。
請求書の電子化は拒否される?
請求書を電子化することで、管理負担の軽減や業務効率化につながるといったメリットが生まれる一方で、相手先に電子化された請求書でのやりとりを拒否されてしまった場合はどうなるのでしょうか。
取引先によっては、社内規則で請求書を紙で扱うことが決められており、電子化された請求書には対応できない、請求書は郵送やFAXで送って欲しいという場合もあります。
企業によって請求書の取り扱いルールは様々ですので、電子化の流れが進んでも、このようなニーズは一定数存在するでしょう。
そのため、電子化に100%移行することが難しいもありますが、一部でも請求書の電子化を進めることで、業務効率化につながるため、電子化はできる限り進める方が効果的です。
また、一部の請求書発行サービスによっては、郵送の代行やFAX送信などのオプションを提供しているものもあるため、電子と紙を併用したい方は利用してみると良いでしょう。
請求書の電子化を拒否される例
請求書の電子化が拒否されてしまう例としては、取引先の習慣によって、紙の請求書のみを取り扱うことが定められている場合です。
多くの企業が業務効率化や管理体制の強化を目的とし、請求書の電子化を進めていますが、中にはツールの利用に抵抗がある、ITリテラシーが低く、PDFファイルなどの取り扱い方がわからないという場合もあります。
そのような場合、請求書の電子化には賛同しにくいでしょう。
また、電子請求書を保存しておくためには、PCなどの端末が必要となります。専門的な業界では、PCを使用していないということも稀にあるため、このような場合は請求書の電子化は拒否されてしまう可能性が高いです。
おすすめのクラウド(Web)請求書発行システム
電子化した請求書の受領を拒否された際の対応方法
電子化された請求書を取引先に拒否された場合の対応方法としては、データを印刷して紙の請求書を発行、郵送やFAXで送付する方法があげられます。
請求書を郵送する場合は、「紙の請求書」「封筒」「送付状」「切手」が必要となります。
ただし、郵送の場合は到着までに時間がかかること、発送にかかる作業の手間が発生する点はデメリットと言えるでしょう。
請求書の電子化は状況によって進めるべき
電子化された請求書について、必要性や拒否された場合などについて解説しました。
電子帳簿保存法の改正に伴い、電子化された請求書の保存要件が緩和されたこともあり、請求書の電子化を進める企業が増えています。
今後、ますます電子化された請求書でのやり取りが増えることが予想されますので、まだ紙でのやり取りが多いという企業は、2024年までの猶予期間が終わるまでに電子化を進めると良いでしょう。
電子化の流れが進んでも、紙の請求書でやりとりを希望する企業は一定数いるため、そちらの対応もできる体制を構築しておくことをおすすめします。