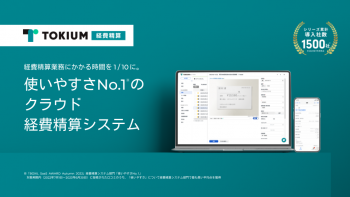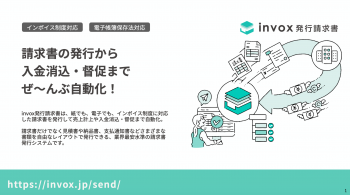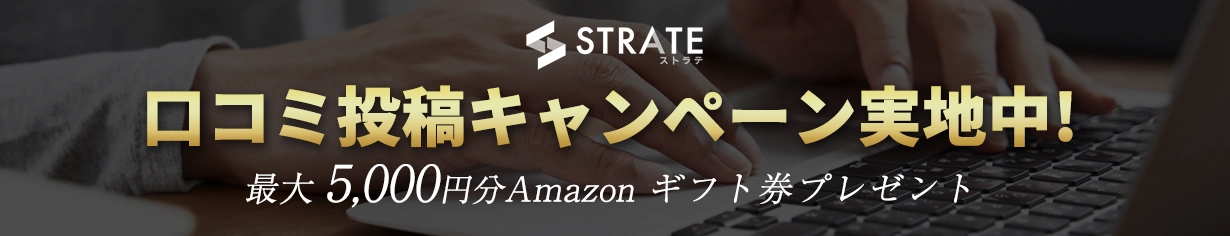電子帳簿保存法の改正によって、請求書を含んだ帳票の義務化が命じられています。
請求書の電子化は、いつまでに対応すればいいのか、何をすればいいのかわからないという方に向けて、本記事では、請求書の電子化に必要な対応や猶予期間などについて解説します。
請求書電子化の義務とは?
請求書電子化の義務とは、2022年1月に「電子帳簿保存法」が改正されたことで、電子取引における帳簿の保存方式として、電子保存形式が義務付けられたことを指します。
法人企業だけでなく、個人事業主も対象となることから、請求書の電子化を疎かにしていると、控除額が少なくなってしまうため、しっかりと準備、対応しておくことが重要です。
電子帳簿保存法とは?
電子帳簿保存法は、帳簿や請求書といった国税関係帳簿書類について、一定の要件を満たしていれば、電子データとして保存することを認めた法律です。
1998年の施行から何度か改正が行われ、2022年の改正において、一部取引における電子保存形式が義務化されています。
請求書や帳票を電子化することで、場所を選ばない業務が可能になり、コロナ禍における生産性の向上にもつながります。
2022年の法改正において、電子データの保存に関する要件が以前より緩和されたこともあり、紙・電子データの書類に関わらずデータとして保存しやすくなったことが特徴的です。
また、電子化の義務化については一定の猶予期間が設けられています。
おすすめの類似請求管理システム
類似サービス: 「楽楽明細」
(4.5)
_商材ロゴカラー.png)
| 月額費用 | 要問合わせ | 無料お試し | トライアル環境あり |
|---|---|---|---|
| 初期費用 | 要問合わせ | 導入会社 | 8,000社超 |
請求書処理の完全ペーパーレス化を実現する請求書の代行受領・データ化サービス。紙・メール・PDF等形式を問わず、取引先から届くすべての請求書を一律で代行受領してくれます。
あらゆる帳票発行の自動化が可能
「楽楽明細」は、請求書や納品書、支払い明細、領収書といったあらゆる帳票の電子化、自動発行が可能です。 帳票データを楽楽明細へ取り込むだけでWebか郵送、メール添付、FAXのいずれかの方法の中から、顧客に応じて自動で割り振り発行してくれるため、書類発行における印刷や封入作業などの手間が大きく効率化されます。
とにかく簡単&シンプル
新しいシステムを導入すると、操作を覚えるために学習期間が必要となることがネックですが、「楽楽明細」は初めてシステムを利用する方でも直感的に理解できる操作性のため、実際に操作しながら覚えることができます。 請求書発行業務に特化した機能が搭載されており、余計な機能がないため、「機能が多すぎて使いこなせない」という課題は発生しません。
契約継続率99%を実現するサポート体制
「楽楽明細」では、導入から実際の運用までを懇切丁寧にサポートしてくれます。無理に契約するようなことはなく、他社比較をした上で納得して契約することが可能です。 幅広い業界の帳票電子化をサポートしてきた経験があるため、業界特有の課題にも対応することができます。
類似サービス: Bill One
(4.5)
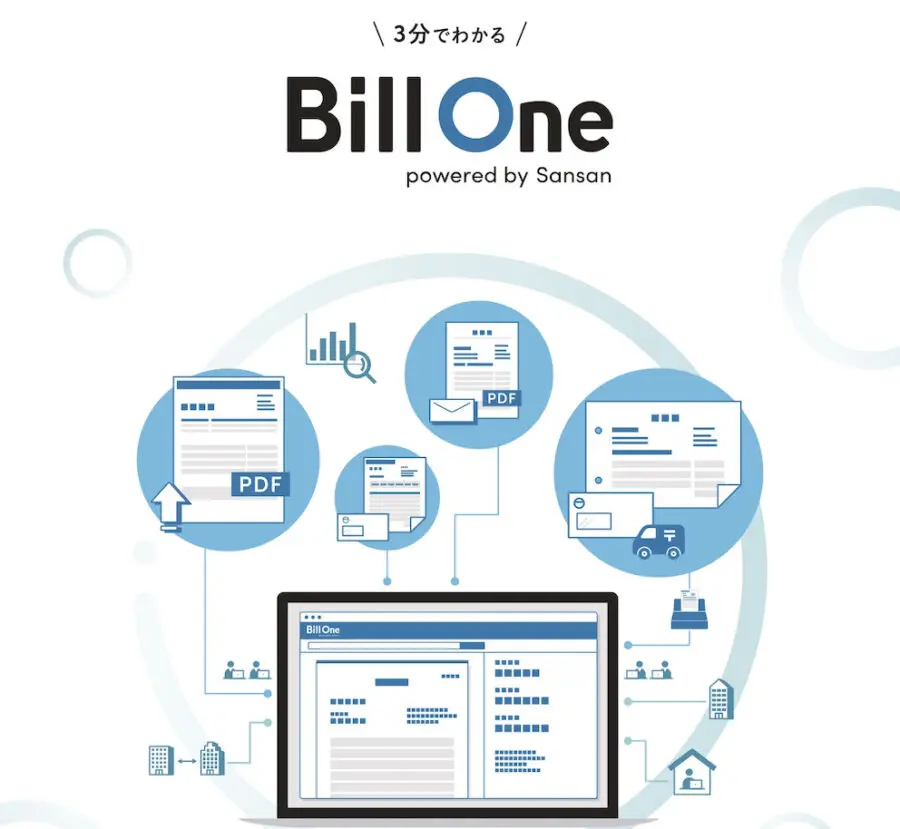
| 月額料金 | 0円〜 | 無料お試し | 要問い合わせ |
|---|---|---|---|
| 初期費用 | 0円〜 | 最短導入期間 | 1営業日から |
Bill Oneとは、Sansan株式会社が提供している請求書管理システムです。 あらゆる請求書をオンラインで受け取ることができ、法改正にも対応。自社で業務フローを変更する手間がかかりません。 拠点や部門ごとにバラバラの形式で届いていた請求書をデータ化して、経理部門を含めた会社全体の請求書業務を効率化、月次決算業務を加速させます。
どのような請求書も電子化可能
Bill Oneは、紙の請求書もPDF形式の請求書もオンラインで受け取ることができるため、請求書の発行元に負担をかけずにオンライン上で受領することが可能です。 請求書を発行する企業は、Bill Oneスキャンセンターへの郵送、専用アドレスへのメール添付、PDF形式でのアップロード、いずれかの方法で送るだけで請求書を電子化することができます。
業務フローを変えずに法改正に対応
電子帳簿保存法やインボイス制度によって、企業は要件に対応した形式での請求書保管を求められています。 Bill Oneでは、適格請求書の発行や登録番号の照合といった機能で、法改正によって求められる要件などに都度対応。導入企業側で業務フローを変更する必要がありません。
外部サービスとの連携でさらに効率化
Bill Oneでは、会計ソフトウエアをはじめとした様々なサービスとの連携によって、請求書に関連する業務をさらに効率化することができます。連携可能なサービスは、今後さらに拡大する予定です
類似サービス: SmartDeal
(4.5)
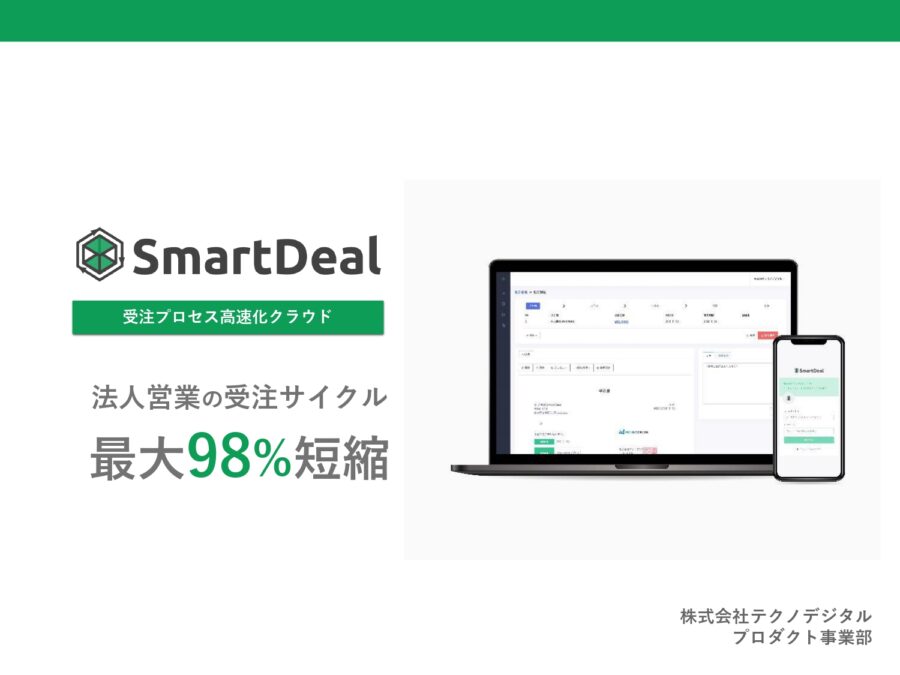
| 月額費用 | 要問い合わせ | 無料お試し | 要問い合わせ |
|---|---|---|---|
| 初期費用 | 要問い合わせ | 最短導入期間 | 要問い合わせ |
SmartDealとは、株式会社テクノデジタルが運営している受注プロセスの高速化を実現するクラウドサービスです。 「決裁者の外出やテレワークによる承認の遅れ」、「書類管理の煩雑化」、「発注・申込作業の遅れ」といった課題を解消し、営業プロセスを短縮することができます。
見積り管理を効率化
SmartDealには、見積りページの作成や編集が可能な機能が搭載されています。 見積りページを作成することで、クライアントが全ての見積り情報・見積書を手軽に確認できるようになります。
書類内容の確認が容易に
SmartDealを導入することで、URLから簡単に書類内容の確認ができるようになります。PC、スマートフォンから確認ができるため、出先やテレワークでの書類チェックのスピードが向上します。 書類内容の修正時にURLを変更する必要がないため、ファイル管理における煩雑化も起きません。
発注・申込もWebで完結
発注や申込がオンラインで完結できるようになるため、営業プロセスの短縮を実現します。 発注側の顧客がSmartDealを利用する上で、ユーザー登録は必要ないため、無駄な作業も発生しません。
請求書電子化の義務化はいつから?
請求書電子化の義務化は2024年1月からとなっています。
2023年12月31日までは猶予期間が設けられており、猶予期間が過ぎた後は、電子取引においては電子保存のみが申告書類として認められ、紙のものは認められません。
コロナ禍によって、テレワークを取り入れる企業が増えたこともあり、書類のやりとりを電子化したデータ形式でやりとりすることが常態化していることもあり、業務効率化などの観点から電子化の流れが強まっています。
請求書の電子化は、法人だけでなく、個人事業主にも義務付けられており、特に青色申告をされているという方は、電子保存の義務が発生します。
電子化の対応を怠った場合、納税する際に青色申告として認められない、または制限されてしまう可能性があるため、注意が必要です。
また、電子化しないことで、控除額が減額となってしまう場合もあるため、個人事業主であっても対応が求めらます。
一方で、法人では、データの保存に関して、隠蔽や改竄などについての罰則が厳罰化されています。
万が一、隠蔽や改竄といった偽装があったとみなされてしまうと、重加算税10%加重されることとなるため、管理には慎重にならなければいけません。
しかし、請求書を電子化することで、テレワークに対応できるようになり、自宅からでも経理処理が可能になるといったメリットもあります。
経理のDX化を進めることができ、その他の業務も効率化しやすくなります。
おすすめのクラウド(Web)請求書発行システム
請求書の電子化を行うことで生じるメリットは?
請求書電子化は、コスト削減・セキュリティ強化などあらゆるメリットを享受できます。
書類管理のスペースが削減される
書類の保存、管理にはそれなりのコストがかかりますが、これらが削減されます。
請求書などの証憑書類は7年間保存する必要があり、紙媒体ではかなりの保管スペースが必要になります。
オンラインで書類データを管理できるようにしておけば、保管スペースを削減でき、ひいては、他の業務のワークスペースに余裕が生まれるのです。
セキュリティ性が向上する
紙媒体の書類は、紛失・破損などの心配が生じます。
また、書類の持ち出し・すり替えなどによって情報が流出してしまう危険がないとは言い切れません。
請求書類を電子データ化しておけば、これらのリスクを回避することができます。
ネットワーク上で保存・バックアップ等を行うことで、情報の紛失・破損は限りなく防止できるはずです。
業務効率が向上する
紙媒体で請求書を保存する場合、ファイリング・ラベリングなどの手間が生じます。
しかし、電子保存を行えば、電子データの保存・ラベリングなどをシステム上で行うことが可能です。
書類の検索や読み出しもオンライン上で簡単に行えるので、経理業務の効率化も図れることでしょう。
請求書電子化義務の猶予期間に対応しておくべきこと
請求書の電子化が義務付けられるまでの猶予期間に、何をすべきなのか、解説します。
個人事業主、法人によって対応すべき内容は異なりますが、最終的には全ての書類を電子化することがゴールとなるでしょう。
しかし、取引先や自社の規制によっては、全てを電子化することが難しい場合もありますので、一部を紙として残し、紙と電子で運用するケースも考えられます。
また、負担が少ない対応方法としては、取り急ぎ必要なものだけを電子化するという方法もあります。
全てを電子化する場合
電子取引、スキャナ保存、電子帳簿保存の全てを電子保存に移行します。
長期的に見れば、全てを電子保存してペーパーレス化することで、データ管理が効率化されるだけでなく、コスト削減にもつながります。
電子化の義務に対応するだけでなく、データ分析をして経理情報の共有に役立てることなど二次的な活用ができる点もメリットです。
義務化が求められる部分を電子保存する場合
電子化が義務付けられているものに関しては、取り急ぎ電子保存を進めて、一部をスキャン保存や電子帳簿保存とするアプローチ方法です。
スキャン保存に切り替えるメリットとしては、紙で帳票を保管していたスペースが不要となるため、オフィススペースの有効活用ができる点などが挙げられます。
また、義務化の範囲となるものに関しては、電子保存対応を進め、残りの帳簿類は会計システムで作成するという方法もあります。
この場合、紙の書類をスキャンする手間を省略することができるため、スキャン作業にあてるリソースがない場合におすすめです。
義務化が必要なものだけ電子化する場合
電子取引において、電子保存が義務化されているものだけ電子化の対応をするアプローチ方法です。
必要なものだけを電子保存するため、現状業務への負荷が最小限で済む点がメリットで、取り急ぎ義務化への対応を進めたい場合はこちらのアプローチ方法が最適でしょう。
ですが、長期的に見ると、全て電子化した方が業務効率化につながるため、タイミングを見て書類の電子化を進めていくことをおすすめします。
余裕を持って請求書を電子化しよう
請求書の電子化に関する義務化は、2024年1月までの猶予期間はあるものの、ギリギリになって対応していると、思わぬミスが発生し、対応が間に合わなくなってしまうこともあるため、余裕を持った対応がおすすめです。
まずは、電子保存が必要となるものを洗い出し、順次対応していくと良いでしょう。