本記事では、インボイス制度や請求書の電子化、文書の電子化についてQ&A方式で解説しております。
インボイス制度についてよくある疑問


A.インボイス制度とはインボイス(適格請求書)の発行あるいは保存によって、仕入税額控除を受けることができる制度です。
この仕入税額控除とは、売上にかかる消費税から仕入れにかかった消費税を差し引くことで消費税の二重課税を解消することができるものです。
こうした制度発足の背景には、令和元年(2019年)10月以降、消費税の軽減税率導入ともない、仕入税額は8%と10%が混在するようになった点が挙げられます。
このためインボイスは各商品の消費税率や消費税額の明記により、それぞれの税率と税額を正確に把握することがその目的です。
これにより、売手は買手に対し、正確に適用税率や消費税額を伝えることができるようになります。
またインボイス制度は売り手・買い手双方に適用されるもので、買い手から求められた場合には必ず交付しなければなりません。
一方買い手は売り手から交付を受けたインボイスは保存しておく必要があります。 ただし、インボイス制度の対象となるのは消費税の課税事業者で、売上が1,000万円未満で消費税の免税事業者として届出をしている場合にはインボイスを発行することはできません。そこで売上が1,000万円未満でもインボイスを発行するためには、届け出によって課税事業者になる必要があります。 しかしながら課税事業者になった場合には、当然ことながら消費税の納税が必要となり、かつ消費税に関わる書類の作成といった負担も増大します。
こうした点から、課税事業者への転換は、課税負担や事業内容などを勘案ながら検討しなければなりません。

インボイス制度への対応が必要な人や企業は?

特にインボイス制度の影響を受けやすいとされるのが売上の規模にかかわらず、次のような業種です。
【飲食業】
飲食業はその仕入れにおいて適用対象が消費税軽減税率である8%と標準税率の10%がそれぞれの混在する業種です。このため、
インボイス制度が開始されると事務処理が複雑化しやすい傾向にあります。
さらに免税事業者から仕入れをおこなっている場合には仕入税額控除を受けることができないことから、インボイス制度の開始によって仕入れコストの増大も懸念されます。
【一部小売業】
規模の小さな雑貨店や、一点ものの作品などを取り扱う骨董店など一部小売業もインボイス制度の影響を受けやすい業種です。これらの業態では個人から仕入れを行うケースも多く、取引相手が適格証明書発行事業者に登録し、インボイスを発行する可能性は低くなります。こうした場合、結果として仕入税額控除ができないことから仕入れコストの増大につながります。
ただし、一定要件を満たしている一部の古物商や質屋であれば「古物商特例」や「質屋特例」といった特例措置により、インボイスの保管義務が免除される場合もあります。
【フリーランス】
フリーランスをはじめとした個人事業主もインボイス制度への対応が難しい業種といえます。
売上高が1,000万円未満のフリーランスであっても「消費税課税事業者選択届出書」を税務署に提出することにより課税事業者となることはできますが、多くの個人事業主は免税事業者として活動していることが大半です。
しかしながらインボイス制度がスタート後は取引先から制度への対応を要求されたり、これが難しい場合には取引を中断される恐れもあります。

インボイス制度導入時に必要な対応は?

【適格請求書の発行】
売り手の場合、必要に応じて適格請求書を発行します。これまで免税事業者だった企業は、インボイス事業者登録を行うことにより、課税事業者になる必要があります。インボイス事業者登録をしなくては適格請求書が発行できないため、要望に応じることができません。登録すれば取引先も仕入額控除が受けられます。ただし、売り手も消費税の納付の必要が出てきます。
【取引先ごとの課税・免税事業者の確認】
買い手は、現在取引をしている取引先が課税事業者か免税事業者かを確認し、新規の取引先ができた場合は適格請求書発行事業者であるかどうかを確認するための業務フローを整える必要があります。適格請求書は課税事業者しか発行できず、仕入れ先が免税事業者の場合は仕入額控除が受けられなくなり、消費税の納付額が上がります。
【インボイス制度に対応できる会計フローの確立】
買い手の課税事業者は、現在使用している会計ソフトをインボイス制度に対応したものに変えなければならないことがあります。インボイス制度により売上税額と仕入税額の計算方法が変わります。そのため、課税事業者と免税事業者で課税仕入を区別しなくてはならないのです。
売り手の場合でも、適格請求書を発行するために新しい書式の請求書を作る必要があります。それだけではなく、適格請求書の写しの保存も義務となるため、対応しなければなりません。

インボイス制度導入で受ける買い手側と売り手側の影響は?

【買い手側】
買い手側にとっては、売上税額と仕入税額の計算方法が変わり、それぞれで計算を行います。
それに、仕入れ先が適格請求書を発行できない場合は仕入額控除を受けることができないので納付する消費税の金額が上がってしまいます。
【売り手側】
売り手側がインボイス制度に対応した場合は、買い手から要求があれば適格請求書を発行します。現在も課税事業者である場合はいいのですが、免税事業者の場合はインボイス制度に対応するとなると課税事業者になる必要があります。支払うお金が増える可能性が出てくるのです。
請求書、文書の電子化についてよくある疑問

請求書の電子化に関する法律はある?

請求書の電子化に関する法律としては、「電子帳簿保存法」が挙げられます。
電子帳簿保存法は、請求書や見積書などの帳票を電子化し、データとして保存することを認めた法律で、1998年の施行から数回改正が行われ、直近では2022年にも改正されています。
電子帳簿保存法では、国税関係帳簿書類と国税関係書類の一部をデータ化して電子保存することが可能です。
また、電子帳簿保存法以外に、e-文書法も書類の電子化に関する法律に含まれます。
e-文書法は、電子帳簿保存法より広義の文書の電子化に関する要件を定めている点が特徴的です。
国税関係の書類だけでなく、建築図書や医療情報に関する記録も、「見読性」「完全性」「検索性」の要件を満たすことで電子化することができます。

請求書を電子化しても法律的に問題ないか

請求書を電子化して、データとして送付することは法律的には問題ありません。
ですが、請求側と受領側で注意すべき点があるため、それぞれに解説します。
【請求書を発行する側】
法律上では、請求側と受領側が、請求書の内容を認識して取引することができれば、電子化したデータでやりとりをしても問題ないとされています。
請求書は、請求に関するやり取りがあったことの証明となるため、税務調査があった際も、データで請求書が存在していれば問題ありません。
ただし、相手企業の社内規制によっては、請求書を紙で保管することを義務付けている場合があるので、その際はプリントアウトの手間が相手側に発生してしまう場合もあるため、取引時に確認しておくと良いでしょう。
【請求書を受け取る側】
請求書をデータとして受け取る側は、請求書の電子化に関する法律で定められた要件を満たさなければいけません。
例えば、e-文書法に定められた要件では、「電子化データがディスプレイなどで鮮明に見れること」「電子化した文書に改ざんなどがないと証明できること」「必要なデータがすぐに検索でき、取り出せること」が条件として挙げられます。
また、過去の請求書をスキャンしてデータとして保存したい場合は、税務署への申請や真実性の確保などが必要となりますので注意が必要です。
電子化にかかる手間はありますが、電子化した請求書は一元管理ができ、欲しいデータをすぐに検索することもできるなど、メリットも多いため、スムーズに電子化できるフローを構築しておくと良いでしょう。

請求書電子化の準備はいつから必要?

改正電子帳簿保存法自体は2022年1月から施行されていますが、以下の要件に該当する事業者については、2023年12月31日までの猶予期間が適用されます。
・保存要件に従うことができないやむを得ない事情がある
・保存が必要な書類を書面で出力した上で適切に保管、提出を求めれた際に対応できるようにしてある
上記の要件を満たしていれば、法律違反となることはありませんが、あくまで猶予期間が適用されるだけで、法律の施行日が延長されるわけではないため、準備は早めにしておくことをおすすめします。
請求書を電子化するための準備としては以下の手順で行うと良いでしょう。
①請求書業務における課題の洗い出し
②課題解決に必要な機能や優先度を決定する
③電子化サービス導入の予算とスケジュールを想定
④電子化サービスの選定
⑤導入
請求書の電子化を進めるにあたっては、まず現状の課題を洗い出し、導入目的を決めることで、最適なサービスを選定しやすくなります。
例えば、オフィスに出社しないと請求業務ができないのであれば、クラウド型の電子化サービスが課題解決に役立ちますし、請求書発行におけるルーティーンワークを自動化したいのであれば、RPAやワークフロー機能が搭載されているサービスが貢献するでしょう。
課題と、課題解決に必要な機能が明確になった後は、サービス導入の概算とスケジュールを想定します。
請求書電子化サービスは、初期費用と月額費用が発生するパターンが一般的ですので、現状の請求業務にかかる人件費や手間を考慮した上でサービス導入における概算をシミュレーションすることが重要です。
また、導入にはどれくらいの期間がかかるのかをベンダー側に問い合わせておくと、余裕を持って導入できます。
サービス選定の際には、デモやトライアルが利用できるサービスを選ぶことで、導入後のギャップを少なくすることができるため、おすすめです。

文書を電子化するメリットは?

【ペーパーレス化の実現】
電子化文書を作ることで、データでのやり取りが行えるようになり、ペーパーレス化が実現します。わざわざ紙を手渡したりする必要がなくなるのでその手間がなくなります。また、紙を保管するための専用の場所を確保することもなくなり、作業スペースを広げることもできるようになります。
【ファイルや中身を検索できるようになる】
文書を電子化するとファイルのタイトルで検索できるようになるので、必要な文書がすぐに見つかるというメリットがあります。何年も前の文書でも、紙だと棚の中を探したりする必要がありますが、電子化されていれば一瞬で見つかります。
【必要なときに共有しやすい】
共有もかなり簡単になります。いつでもどこでも同時に文書を閲覧できるので、コピーして配布する必要がありません。また、文書の修正の必要があったとき、修正前の文書を残せるため元に戻したいという場合も迅速に対応できます。
【紛失リスクが軽減する】
紙の文書の場合は、書類を棚に片付けて数年が経過してしまうのはよくある話です。急にその文書が必要になったとき、置き場所を忘れてしまい大捜索を行うという経験がある人は少なくありません。文書が電子化されていれば、データ管理・バックアップ・セキュリティ対策をしっかりと行うことで紛失リスクの軽減が可能です。多くの文書をわかるように管理したいという場合にも対応できます。

文書電子化の注意点は?

【情報漏えいには気をつける】
文書を電子化すると、データの1つとして扱われます。フォルダ・ファイルごとのアクセス権の設定を行い、部署間のやり取りを行うときのルールを決めましょう。それに加え、セキュリティソフトなどで対策を行い、情報漏洩が起きないようにしましょう。
【関連する法律にも注意する】
文書を電子化する際、法律に注意しなければならない場合があります。民間での文書の電子保存を容認している「e-文書法」、国税関係帳簿書類の保存における、所得税法や法人税法などの特例を定めている「電子帳簿保存法」の2つは要チェックです。

文書を電子化する方法は?

【スキャナでPDF化する】
最も簡単な方法は、コピー機や複合機のスキャン機能を利用することです。元々ある機械の機能を利用するためコストがかからず、業務の合間に少しずつ進めることができます。
【文書管理システムなどを使用する】
文書管理システムの利用も1つの方法です。文書管理システムは、電子化された文書を格納し、保管・保存・活用・廃棄を一元管理するシステムです。文書の整理・更新・共有にはもってこいのソフトで、企業だけではなく総務省や自治体でも活用されています。
電子領収書についてよくある疑問

電子領収書のメリットは?

【印紙税がかからない】
紙の領収書の場合、一定額以上の記載金額になると収入印紙を貼らなければなりませんでした。ですが、電子領収書は印紙がいらないため、印紙税が節約できます。
【紙の保管スペースが不要】
領収書は7年間の保管が法人税法で義務づけられています。そのため、紙の領収書を保管するスペースを確保しなければなりませんでした。電子領収書も7年間保管しなくてはなりませんが、パソコン内やクラウド上の保管が可能なので管理スペースが必要ありません。
【必要な領収書をすぐに取り出せる】
紙の領収書を探す場合、インデックスなどで整理されていないと見つけるのは困難です。電子領収書は、ファイル名で検索をかけることができるのですぐに見つけることができます。デスクを離れる必要もないので、作業の効率化に繋がります。

電子領収書を発行する方法は?

【法律や必要な要件を確認する】
まずは電子領収書に関わる法律や要件を確認する必要があります。取引関係の書類を電子データで保存することを定めている電子帳簿保存法が重要なチェック項目です。
領収書の保存期間は、事業年度の最終日から2ヶ月が経った次の日から7年間とされています。あらかじめいつまで保管しておくかをまとめておくとわかりやすいでしょう。
【社内運用体制の構築】
社内で電子領収書を扱うための体制の構築をしておくと、スムーズな運用が可能です。どのように電子領収書を作成するのか、システムを導入するのか、控えの方法はどうするのかなど、扱い方によって業務フローが変わってきます。状況に応じて柔軟な対応をしていきましょう。
【ツールやシステムの導入】
電子領収書に対応したシステムを導入するとなると、やはりコストがかかります。初期費用やランニングコストなどはシステムによって異なるため、利用したい機能や使いやすさ、既存のシステムとの連携などを確認して比較するようにしましょう。
【税務署へ申請する】
電子化された領収書やレシートを有効にするには税務署への申請が必要です。電子化したと言ってすぐ紙の領収書を処分してもいいというわけではありません。まずは申請を行うために、税務署、税理士に相談してみましょう。
帳票についてよくある疑問

帳票OCRのメリットは?

【ペーパーレス化が進む】
紙の帳票もありますが、ペーパーレス化により帳票の電子化が進んでいます。帳票OCRを導入することで、紙からペーパーレスへの移行が楽になり、対応もスムーズになるのです。
やり方は簡単で、複合機やスキャナーを利用して文書を画像やPDFで取り込み、パソコンへ転送します。そうすることで帳票の情報が電子化されるため、電子コンテンツの1つになります。
【データを一元管理できる】
帳票の電子化により、データの一元管理が可能になります。保存場所がPC内の1ヵ所にまとまり、取り出すときも便利です。それに、社内規定のフォーマットの作成や用意されたテンプレートを使用して公的書類の作成もできます。
【必要なデータをすぐに検索・共有できる】
電子化したファイルには必ず名前をつけます。パソコンのファイル内は検索ができるので、ファイル名を検索するだけで見たいファイルがすぐに見つかります。なので、ファイルに名前をつけるためのルールを決めておくといいでしょう。また、メールに添付するなどで共有ができるようになるので、わざわざコピーして手渡しをする必要がないのもメリットです。
【手入力によるミスや手間を削減できる】
帳票OCRの機能の1つに、各フィールドの入力データのチェックがあります。この機能を利用することで、認識データの誤りや不備を見つけ、帳票業務の品質を高めることができます。手入力で起きるミスを削減し、修正の手間が減ります。

帳票OCRソフトの選び方や比較ポイントは?

【普段使用している帳票に対応しているか】
認識可能な帳票は、フォーマットが決まっている帳票である定型帳票、項目は同じだけれどもフォーマットが定まっていない準定型帳票、項目や記載位置に規則性がないタイプの非定型帳票の3種類です。定型帳票のみが対応しているソフトもあれば複数の帳票タイプに対応しているソフトもあります。自社の帳票がどのタイプなのかを確認し、合うソフトを導入しましょう。
【電子化したい帳票の量で選ぶ】
手書きの読み取りのために帳票OCRを使いたいという場合、1文字あたりの単価で読み取りができるサービスもあります。どんな種類の帳票が多く、どれくらいの帳票をテキスト化しなければならないのかを把握しておくことで、検討の目安となります。
【文字認識の精度】
文字認識能力も重要なポイントです。帳票には活字はもちろんですが、手書きやチェックボックスやマークなど、様々な文字が入り混じっています。これらの文字を正確に認識できるかどうかで大きく差が出ます。文字認識のためのエンジンを複数搭載しているソフトなら、精度の高い文字識別が可能です。
【出力方法の種類や外部システムとの連携】
帳票OCRで電子化したデータをサーバーに保存し、他の業務システムでも帳票業務ができる連携機能があれば、業務効率がよりアップします。CSV出力対応機能もあると、いろいろなソフトで編集が可能になります。
【価格】
金額も重要な比較ポイントです。どんなにいいソフトでも、予算に見合ったものでないと金銭的な負担が大きくなり、ソフトのために無理をすることになってしまいます。無理のない金額のソフトを選ぶようにしましょう。
請求書の取り扱いについてよくある疑問

請求書の保管方法は?

【紙でファイリング】
請求書を印刷し、紙でファイリングする方法です。
請求書を整理して保管するための専用のスペースが必要ですが、操作が簡単で直感的な方法です。
【OCRなどで電子化】
OCR(光学文字認識)などの技術を使って請求書をスキャンし、デジタルデータとして保管する方法です。
紙の請求書を電子化することで、保管スペースの節約やデータの検索・管理が容易になります。
【システムでデータ管理】
請求書管理システムを導入することで、請求書データをオンライン上で管理できます。
データの入力や検索、保管期限の管理などが自動化され、手作業の手間やヒューマンエラーのリスクを減らすことができます。

請求書をシステムで管理するメリットは?

【電子帳簿保存法に対応】
システムで請求書データを管理することで、電子帳簿保存法の要件に適合できます。
電子データの保存や閲覧、プリントアウトなどが容易に行えます。
【紛失リスクが少ない】
紙の請求書は紛失や破損のリスクがありますが、デジタルデータとして管理することで紛失リスクを低減できます。
さらにバックアップやセキュリティ対策を施すことで、データの安全性も高められます。
【保管スペースが不要】
紙の請求書を保管するためにはスペースが必要ですが、データ管理システムを利用すると保管スペースの必要性がなくなります。
オフィスのスペース効率が向上し、スッキリとした環境を実現できます。

請求書の送り方の流れは?

【請求書の発行】
請求書を作成し、必要な情報(請求内容、金額、支払期限など)を記入します。
正確でわかりやすい請求書を作成することが重要です。
【請求内容の確認】
作成した請求書の内容を再確認し、誤りや漏れがないかを確認します。
金額や商品・サービスの詳細など、請求内容が正確に記載されていることを確認しましょう。
【送付先の確認】
請求書を送付する先の情報(会社名、住所、担当者名など)を確認しましょう。
送付先情報が正確であることを確認することで、請求書が適切な宛先に届くようになります。
【送付方法を決めて送る】
請求書を送付する方法を選択しましょう。
郵送、メール、専用のシステムなど、送付方法はさまざまです。適切な方法を選び、請求書を送りましょう。

請求書の具体的な送り方は?

【郵送で送る】
請求書を封筒に入れ、郵送する方法です。
請求書の発行から宛先への到着までの時間がかかる場合がありますが、受取確認の手続きが不要であるため、一般的に利用されています。
【メールで送る】
請求書をPDF形式などで作成し、メールで送付する方法です。
迅速に請求書を届けることができますが、電子メールのセキュリティ対策や送信後の確認が重要です。
【専用のシステムで送る】
専用の請求書管理システムを利用して請求書を送付する方法です。
データ入力や送信手続きが簡略化され、効率的な請求書の管理が可能となります。
システムによっては自動的な送付や支払いの管理などの機能も備えています。
まとめ
インボイス制度や請求書の電子化への対応は今後必須になるものです。
必要な知識を学んで、請求書への適切な対応を行うべきでしょう。

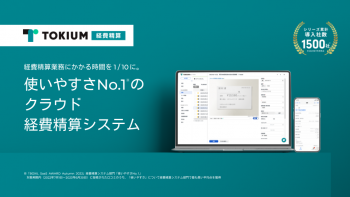

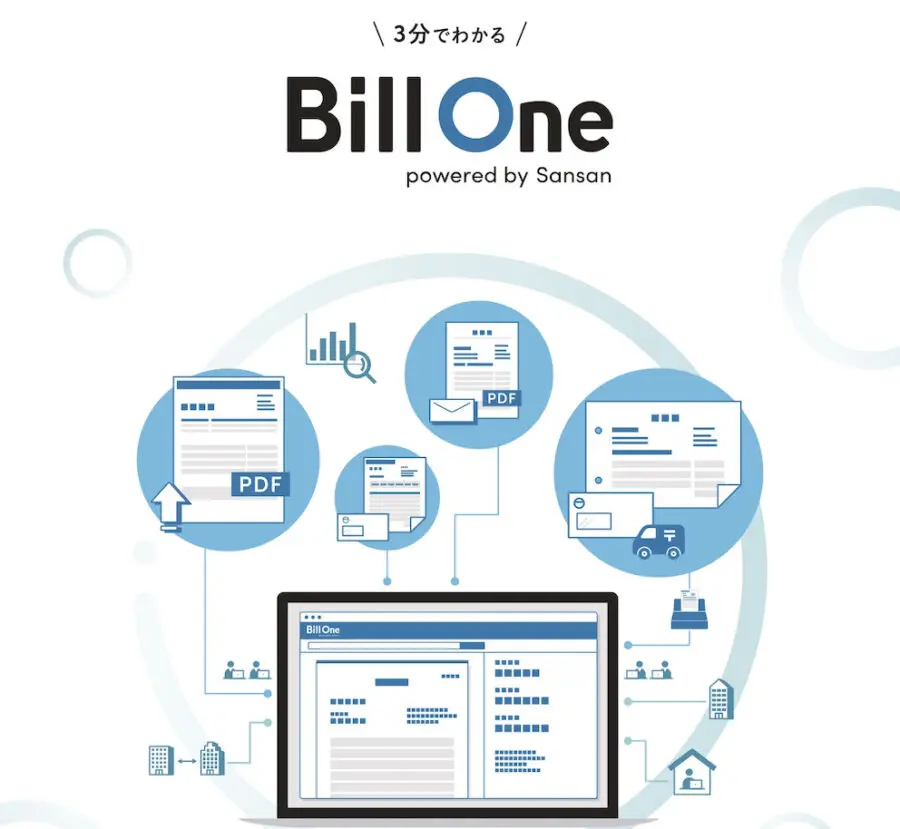
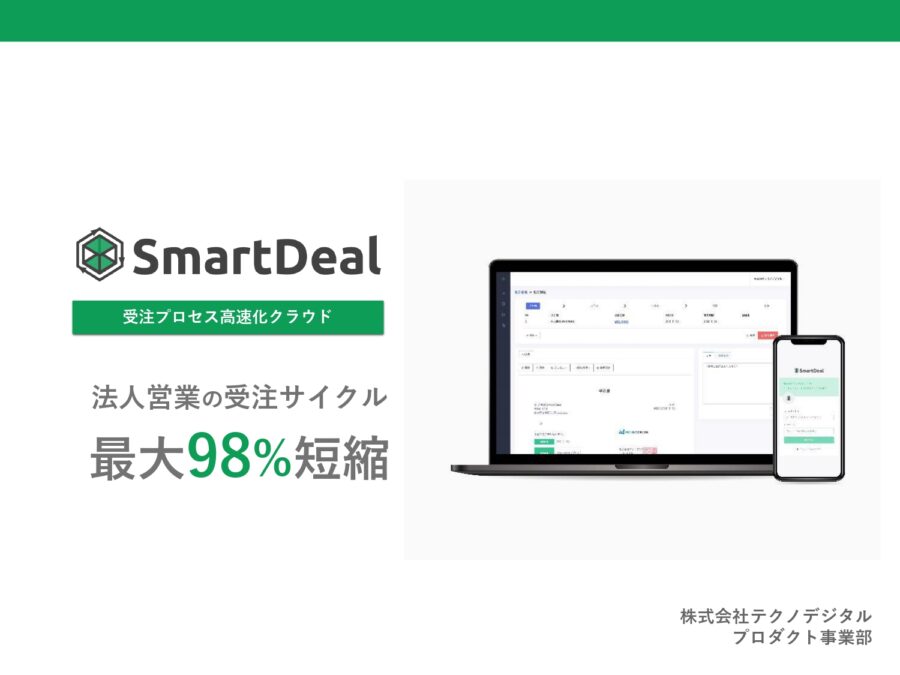

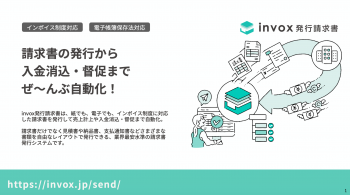

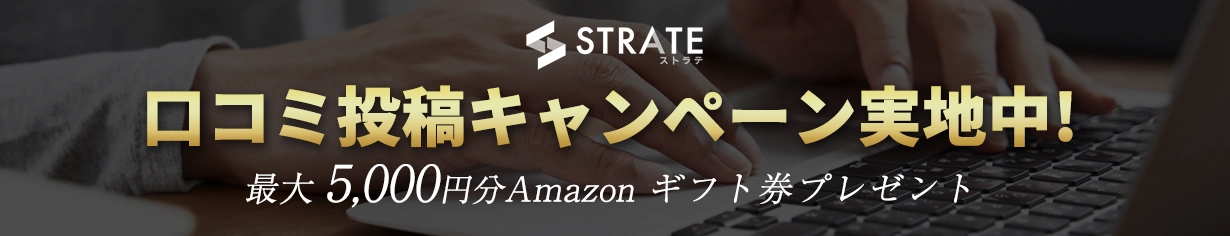
Q.インボイス制度とはどんな制度?